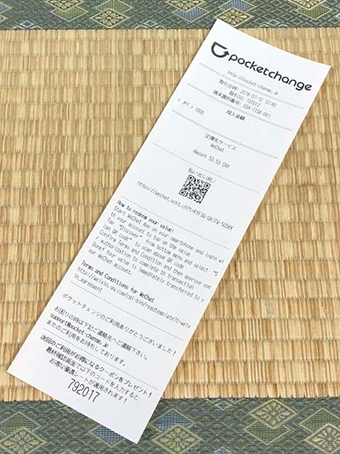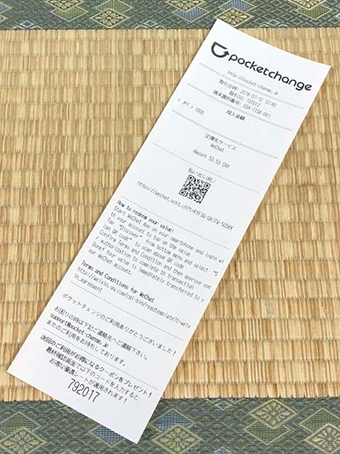■電子決済が急速に普及した理由は?
一般的に中国で電子決済が急速に普及した理由は、「ニセ札問題」説が有力です。
しかし、実際に現地で様子を目の当たりにすると、現金が使えない訳ではないので、「ニセ札問題」が全てではないようです。また、WeChat PayのようなQRコードを用いるシステムは、日本で主流の電子マネー「Felica」(ICを利用)に比べると、セキュリティー面での心配が残ります。最近、QRコードのみで簡単に決済できるのは1日に500元(9000円程度)の上限が設けられ、被害の心配が小さくなり、また犯罪抑止の効果もありそうですが、今後はシステムの改善が求められそうです。
筆者の私見ですが、スマホ決済が普及した理由を整理すると:
1. 必需品となったスマホに加え、財布も持ち歩くのが面倒に感じるようになった。
2. システムの導入コストが低い。クレジットカードが導入できない零細店舗や個人も向く。
3. 小銭のやり取りが不要に(省力化)。支払い側が暗算で小銭を減らす工夫はしない。
4. 現金に比べ、紛失や盗難時に被害が少ない。
、といった所でしょうか。
特に旅行や出張などで、短期滞在者の場合、コインを見分けるのも億劫なもの。一度体験して使えるようになれば、スマホ決済はとても快適です。
■日本人が利用するには??
「WeChat Pay」を利用するには、原則として、中国で銀行口座を開設する必要があります。
駐在員などの長期滞在者なら口座を開いて当然でしょうが、出張や旅行では難易度が高いと言えます。
最も簡単な方法は、「WeChat Pay」利用者から送金をしてもらう事。送金により、中国に口座を持っていなくても、「WeChat Pay」が利用できるようになります。
「WeChat Pay」にお金をチャージするには、やはり中国の銀行口座が必要ですが、少額を試してみたいなら、pocket changeという端末が利用できます。そもそもpocket changeとは、旅行などで手元に残った海外通貨(少額で換金し難い)を、電子マネー化するサービスで、主に空港などに設置されています。そのため、交換レートは現金よりも不利で、大金の換金には向きませんが、数千円相当を「WeChat Pay」を試してみたい…という目的なら充分に実用的です。

【写真】pocket change 端末。空港の国際線ターミナルなどに設置されている。
【写真】「WeChat Pay」入金すると発行されるレシート。スマホの「WeChat」アプリでQRコードを読み取る。
【キャプチャ画像】チャージが完了すると、スマホ画面で残高が確認できる。「\」は、中国人民元(圓)の意。
■ さいごに
日本では20年以上も前に、ソニーがFelicaという電子マネーを想定した技術やシステムを開発し、現在では、Suicaなどの交通系を筆頭に、数多くのサービスが登場。広く普及するに至りました。その流れで、スマートフォンでも、電子マネー対応となると、Felicaに準じたハードウェアを搭載することになり、セキュリティーや使い勝手の面では優れたポイントが多くあるものの、比較的安価なスマホ製品では利用できなかったり、店舗にも対応するICカードリーダーを設置する必要など、ハードルの高さは否めません。
最終的にセキュリティーを重視したICタイプが残るのか、あるいは、急速に普及し、利用者数の急増で存在感を増す、「WeChat Pay」のようなQRコード¥(バーコード)タイプが残るのか、あるいはブロックチェーン技術を利用する仮想通貨が全てを呑み込むのか。大きな変革期を迎え、新しいビジネスチャンスも生まれそうです。