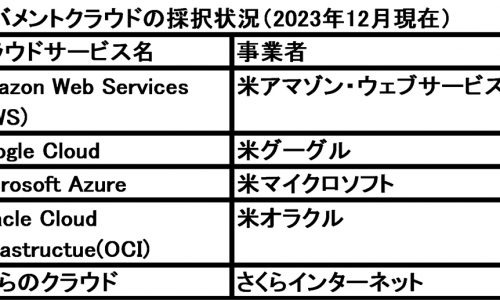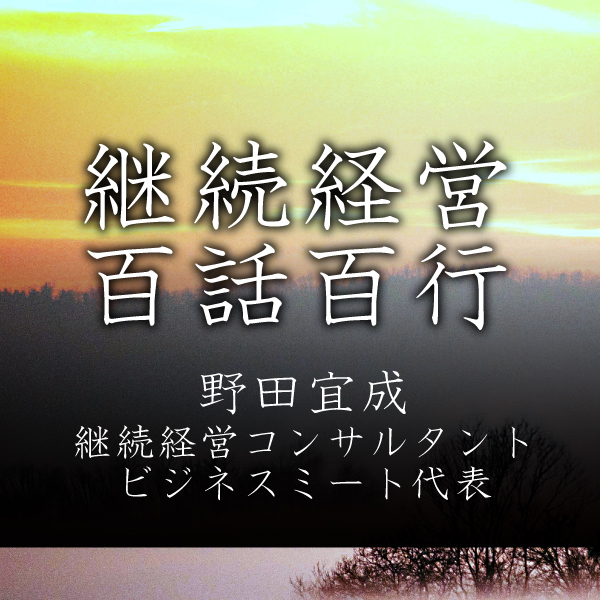アヘン戦争と天保の改革
徳川幕府という政体は柔軟な組織運営によって、体制危機を巧みに乗り越えてきた。将軍の代替わりごとに起用した幕閣たちが時代変化に合わせた改革方針を打ち出して、堅固な支配体制を永続させてきた。しかし19世紀に入ると、危機の質は深刻化する。内に目を向けると天保年間には毎年のように飢饉が襲い、各地で貧農、社会弱者たちの暴動が頻発する。さらに外からの危機要素として欧米列強の開国圧力も露骨化してくる。浜松藩主の水野忠邦(みずの・ただくに)が老中首座となったのは、こうした内憂外患に取り巻かれた1839年(天保10年)のことである。彼は政治改革に取り組む。天保の改革である。
支配体制強化のための財政改革に取り組む水野の耳に、アヘン戦争(1840〜42年)の情報が飛び込んでくる。中国(清)がアヘンを強引に売り込む英国を排除しようと戦って敗れたというのだ。清は、多額の賠償金を要求され香港を割譲させられたという驚愕の事態だ。さらにオランダ船を通じての情報によれば、「英国の次の目標は日本で、軍艦を派遣して通商を迫り、日本の対応次第では武力に訴える計画だ」という。
水野は、繰り返される凶作による年貢米の減収で逼迫する財政事情の中で、国防強化に乗り出すことになる。長崎のオランダ商館経由の情報で西洋事情に通じている水野は、欧米の目覚ましい軍事力の発展を知っている。太平の世を貪ってきた日本の軍事力は衰退するばかりで、このままでは戦えない。外国船の襲来に備えて国防の態勢構築が急務だ。水野が指揮を執って西洋砲術の習得を急がせ、鉄砲隊を整備し、江戸湾の防塁建設を急がせる。
幕府政策大転換は弱腰か
そして外国船への対処方針で、大転換がもたらされる。沿岸に近づく外国船があれば砲撃し接近を阻止する「異国船打払い令」(1825年発令)を解除し、漂着船に対しては燃料・水を提供して丁重に扱えという方針に大転換した。新しい世界情勢に対して、「鎖国は国の祖法である」などと建前では対処できない。現実を見て合理的に対応する。開国の一歩である。
軍事力に格段の差がある欧米諸国との間で不用意なトラブルを避ける。それに向けた現実的な方針転換であり、対等の国防力を手に入れるまでの時間稼ぎだった。彼我の力量差を踏まえた上での臥薪嘗胆(がしんしょうたん)の心構えであった。この方針が、その後、砲艦を押し立てて開国を迫ってきた米国のペリー黒船来航への対処、日米和親条約、日米修好通商条約へと繋がっていく。
しかし、一連の対外方針が、尊王攘夷派から「幕府の無策、弱腰外交」と非難され、倒幕への動きを加速させることになる。しかし、朱子学とナショナリズムが結びついたイデオロギーとしての浅薄な攘夷を掲げ、藩をあげて幕府批判を繰り広げた長州藩は、四国艦隊を相手にした下関戦争にあっけなく敗れる。朝廷を政治から遠ざけてきた幕府への憎しみで凝り固まる孝明天皇は、幕府に執拗に、出来もしない「攘夷の即時実行」を迫り続ける。どちらが日本にとって正しい国策判断だったかは火を見るより明らかだろう。「攘夷」を唱えれば、神風が吹いて敵を打ち破れるとでも思っていたのか。これでは13世紀の元寇に対処した呪術の世界だ。
「攘夷」とその象徴としての天皇を反体制運動の求心点として利用し幕府を倒した政治勢力は、明治維新後の日本を、空疎な「神風期待の富国強兵」の道へと引きずり込んでいく。歴史の事実だ。
即時攘夷は単なるイデオロギー
アジアの大国である清が、軍事力で圧倒する英国に無謀な戦いを挑んで敗れ、侵食されていく姿を見て、水野以下の幕末の幕閣たちは、驚愕すると同時に、対処を考えた。まずは国防力の強化が必要だと。実際に幕府は海浜の防衛を強化すると同時に、海軍力の整備に乗り出し、近代的な陸軍の創設にも動いている。理不尽な外夷に対抗するという意味での「攘夷」を言うなら、幕府も攘夷派だった。
中身のないイデオロギー攘夷を振りかざした尊皇派が、実現不可能な「即時攘夷実行」を訴える時代の空気の中で、幕府は、国の運営に責任を持つ立場で、開国やむなしと考え、その先を見据えていた。「即時攘夷派」に対して長期的視野で国のあり方を考える「未来攘夷派」と言えるのではないか。
幕末の歴史を見る筆者には、そう見える。しかし、多くの幕末物語では長州、薩摩の勤皇の志士たちはみな英雄であり、将軍、幕閣たちは事態に対処できない頑迷固陋な無能人士として描かれ続けてきた。
幕府を倒した「勝者」が書いた歴史とは、そんなものである。勝者の歴史は、距離をおいて読んだ方がいい。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『近世の三代改革』藤田覚著 山川出版社
『攘夷の幕末』町田明広著 講談社学術文庫
『日本の歴史18 幕藩制の苦悶』北島正元著 中公文庫