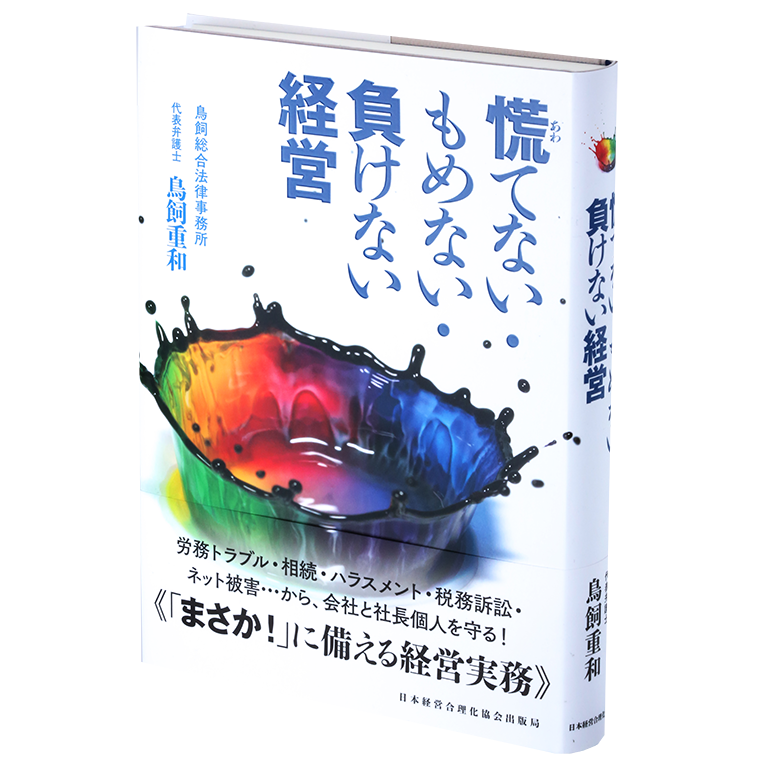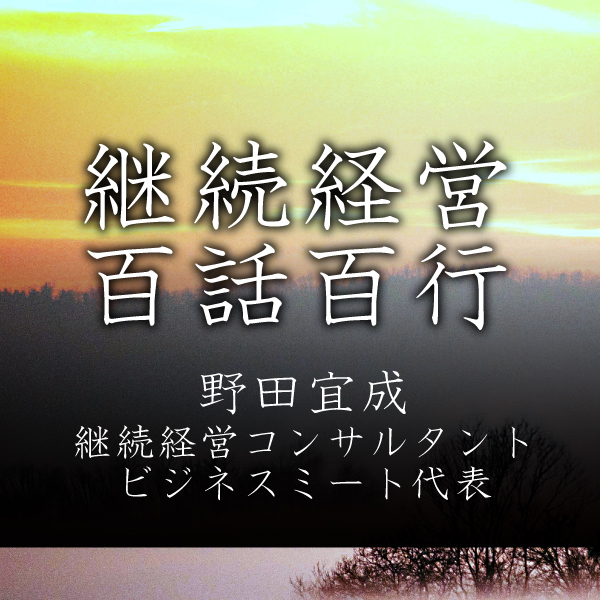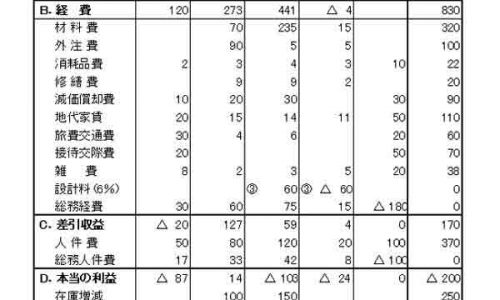- ホーム
- 中小企業の新たな法律リスク
- 第32回 『テレワークを導入するにあたって気を付けるべきこととは!?』
新型コロナウイルスの影響で、世間で良く聞かれるようになったテレワークについて、太田社長も導入を検討したいとのことで、それについての相談のようです。
* * *
太田社長:賛多先生、今日はマスクをしたままで失礼します。しかし、この度の新型コロナウイルスで世間は大変な状態ですね。私の知り合いの経営者で、特にBtoC(Business to Consumer)のビジネスを行っている会社は、軒並み大打撃らしいですわ。
賛多弁護士:太田社長、私もマスクをしたままで失礼します。もしお気になるようでしたら、窓を開けて換気しますので、おっしゃって下さいね。令和最初の国難といっても過言ではない状況で、皆様大変な状況と推察します。他の顧問先の方々からも、従業員やお客様に感染者や濃厚接触者が出たらどうしたらいいのか、時差出勤やテレワークを導入した方がいいのか、といった質問を受けているところです。
太田社長:先生、今日はまさにテレワークについてお聞きしたいのです。従業員から、満員電車の通勤は感染リスクがあるので怖い、学校が休みになって子供が家にいるので自宅で働けないのかなどといった要望が出てきているところなのです。テレワークが自宅などで勤務するということはマスコミからの情報で分かったのですが、正直細かな点までは理解していないのです。テレワークを当社で導入できるのか、できるとしてどのように進めればいいのか、ご相談したいのです。
賛多弁護士:なるほど、了解しました。まずテレワークとは、働く場所や時間にとらわれずに柔軟に働くことをいい、自宅でパソコンや携帯電話、FAXを使って働く「在宅勤務」の他に、顧客先や移動中にパソコンや携帯電話を使って働く「モバイル勤務」、会社以外のオフィススペースを使う「サテライトオフィス勤務」などがあります。今回の新型コロナウイルス対策のような場合は、感染防止の意味合いが強いので、自宅で働く「在宅勤務」が中心になると思います。
太田社長:なるほど。ところでテレワークを導入した場合、会社はもぬけの殻になるのでしょうか。
賛多弁護士:たしかに、全従業員に在宅勤務を行わせる企業もありますが、必ずしも全従業員に適用させる必要はなく、また連日在宅勤務を継続する必要もないのです。つまり、テレワークを導入するとして、会社が対象者の範囲や実施日などを決めることができるのです。ただ、裏を返せば会社が決めなくてはならないということでもあるのです。
太田社長:テレワークに向いている業種や職種というものはあるのでしょうか。
賛多弁護士:一概にこれが向いている、というものはありませんが、まず業種ですと、直接消費者と相対する業種を除き、概ね導入可能であると思います。職種に関しては、現場での作業が必要不可欠なもの以外であれば導入可能であると思います。
太田社長:なるほど、対象は幅広いのですね。先生もご存じの通り、当社はスマホ向けのアプリやゲーム開発を行っているので、直接消費者と接する訳ではなく、導入可能ということですね。
賛多弁護士:その通りです。あとは社長もご懸念の通り、どのように導入するかがポイントです。先ほどお話した対象者の範囲や実施日はもちろんのこと、テレワークは会社以外の場所での就業ですから、勤務場所や労務管理方法、情報セキュリティ、勤務場所での就業環境などを検討した上で決定する必要があります。
太田社長:何か従業員と契約を結ぶ必要はあるのでしょうか。
賛多弁護士:テレワークの導入と内容について、就業規則を修正するか、別途テレワーク勤務規程を作成し、従業員の皆様に説明することなどが必要となります。尚、テレワーク勤務希望者には、別途希望届を出してもらい、会社が承認する形で実施することが望ましいです。
太田社長:分かりました。しかし、色々と検討しなければならない点があるのですね。まずは何から始めればいいのでしょうか。
賛多弁護士:はい、まずはテレワーク対象者の範囲と実施日の決定ですね。部署や職務内容を踏まえ、その人がテレワークを実施可能かどうか、実施可能であるとして対象者とするかどうか、例えば、入社して間もない人は除外するなどが考えられます。実施日ついては、例えば月曜と金曜は出社してもらい、その他の日はテレワーク、ということなどが考えられます。
太田社長:分かりました。一度社内に持ち帰って、人事担当役員と協議します。その上で改めて先生とテレワーク導入について協議させてもらえますか。
賛多弁護士:もちろんです。承知しました。
* * *
今回の新型コロナウイルスで、テレワークとの言葉を耳にする機会が増えました。テレワークはワークライフバランスの実現や生産性の向上、コストの削減、環境負荷の軽減などのメリットがありますが、一方で導入にあたっては、対象者の範囲や実施日の決定、労務管理方法や情報セキュリティ確保の検討など、多岐にわたる検討が必要となります。導入を検討する場合、専門家と協議しながら進めましょう。
執筆:鳥飼総合法律事務所 弁護士 丸山 純平