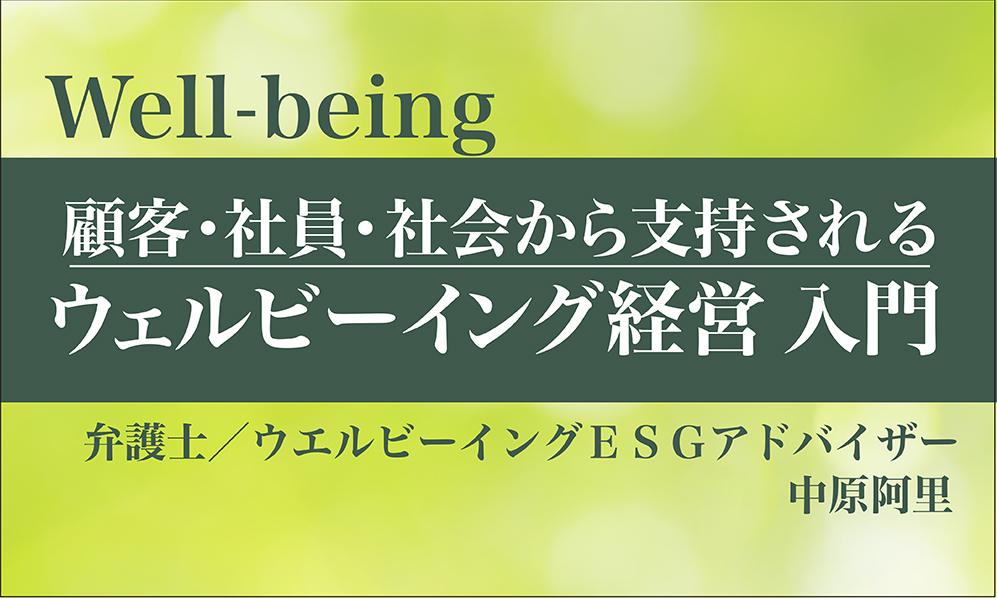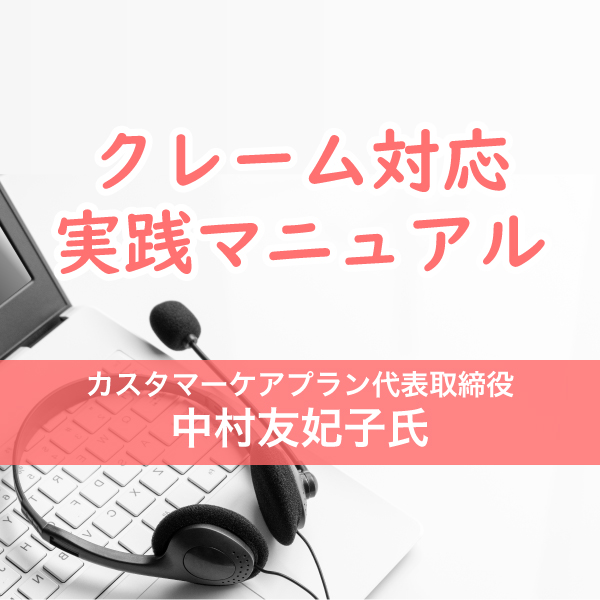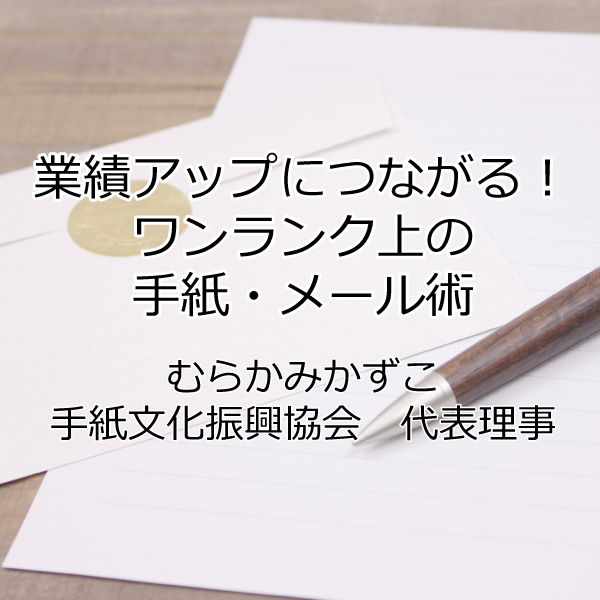横領、情報漏えい、粉飾決算、表示偽造、ハラスメントなど、企業での不正やコンプライアンス違反事件は後を絶ちません。本コラムをご覧の経営者の方は、「まさか、うちの会社に限って」とは思っていませんよね?
残念ながら、不正はどんな組織でも起き得ることです。そして、ひとたび不正が明るみに出れば、会社の信用は失墜し、取り返しのつかない事態に陥ることもあります。
また、不正は企業業績を悪化させるだけでなく、経営陣の責任問題にもつながるという意味で、経営人生に大きく影響します。もちろん、働く従業員の人生をも狂わせる可能性があります。今日は、企業不正について、ウェルビーイング経営の観点から考察するとともに、カギとなる不正のトライアングル理論もご紹介します。
1 コンプライアンス違反が起きるメカニズム
そもそも、なぜ組織で不正が起きてしまうのでしょうか。不正はいけないことだと誰しもがわかっているのに、どうして不正は絶えないのでしょうか?
この点について、アメリカの組織犯罪学者であるドナルド・R・クレッシーは、職場での不正の原因として、「動機」「機会」「正当化」という「不正のトライアングル」理論を提唱しています。これは、人が組織内で不正を起こす時、この3つの要素が同時に成立しているというものです。
2 不正のトライアングル3つの要素
①「動機」の存在
ここでいう「動機」とは、本人が不正を行う精神的な引き金となるものです。
例えば、金銭的に困っている、職場の人間関係が悪い、仕事のストレス、会社に対する信頼感の薄さ、などが挙げられます。
もちろん、金銭的に困っているからといってすぐに不正に走るわけではありません。人間関係の不良さや、職場へのストレス、信頼感の薄さなどが相まって横領などの不正に走る動機が形成されていくわけです。
②「機会」があること
「機会」とは、本人に不正行為を可能とさせるような状況を指します。
現金や小切手の管理権限を持つ立場、重要な情報を知り得る立場、あるいは権限者への管理システムの甘さなどがこれに該当します。牽制が働かない状況や、ルールが曖昧な環境は、不正の温床となりやすいのです。
③「正当化」ができること
「正当化」とは、本人が不正行為を合理化する余地のことです。
「これくらいなら大したことないだろう」
「最初は故意の無いミスだったが、誰も気づかないから繰り返してしまった」
「他の人もやっていたから」
など、いわゆる言い訳に近い状況です。こうした正当化は、本人の倫理観の欠如に起因することもありますが、多くの場合はそれだけではありません。
職場全体の規範意識の低さや、空気感が「正当化」を知らずと促しているケースも多数存在しています。小さなことでも、しっかりとフィードバックするなど、健全な職場環境を常に意識していかなければ、不正を「正当化」する隙を与えてしまいます。
これらの3つの要素が同時に発生し、いわばトライアングル状態になったときに、不正事件は起きやすくなると考えられています。
例えば、借金返済に困り、会社には相談できる関係もなく、売り上げ達成プレッシャーに負われて高ストレス下にあり(動機)、店長として売上金を動かす権限があり(機会)、最初は「少しだけ」「後で補充すればよい」という気持ちで売上金を持ち帰ってしまったところ、誰からも指摘されないため(正当化)繰り返してしまい、多額の横領事件に発展する、といったケースは実際に後を絶ちません。