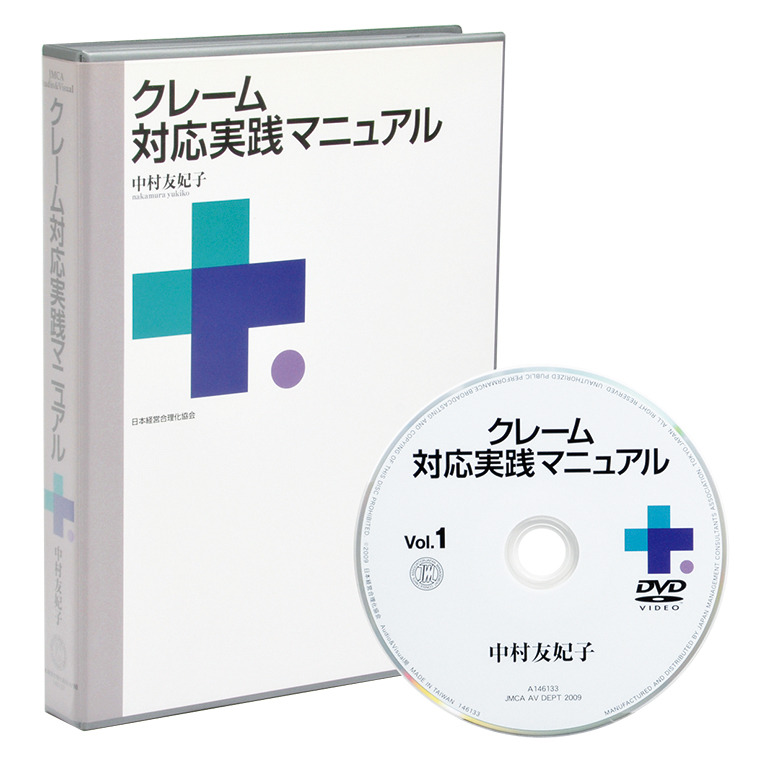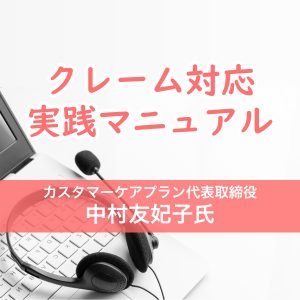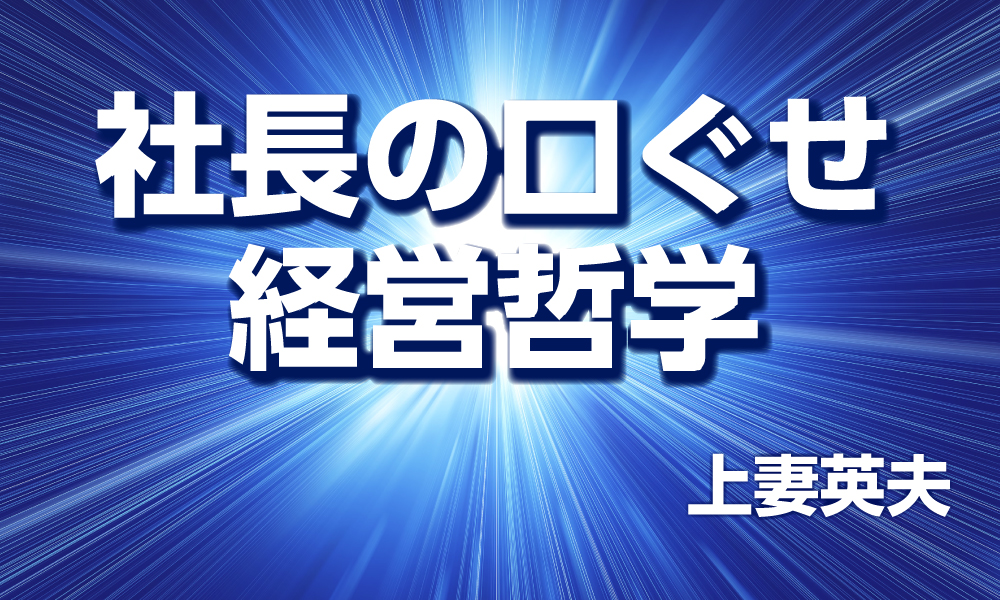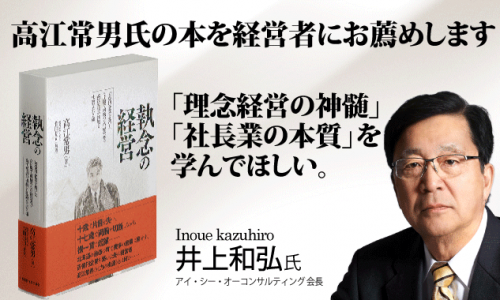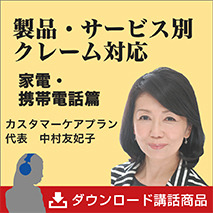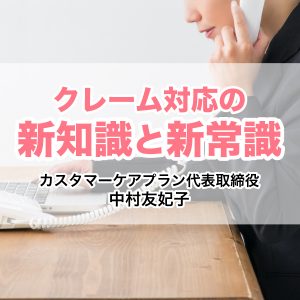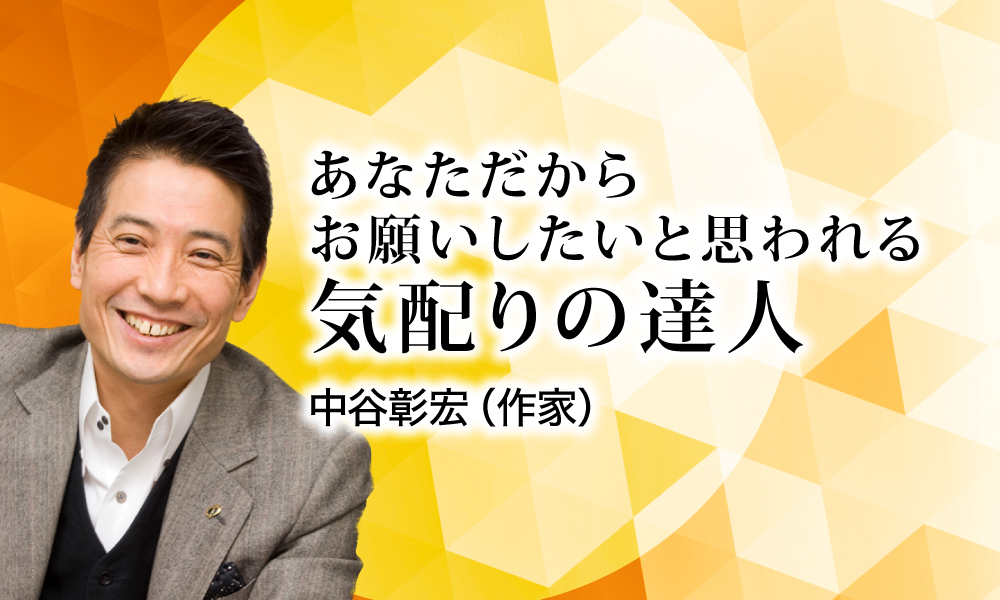お客様の声を商品に生かす企業になろうとか何とか言いながら、消費者から遠い部門になればなるほど、めんどくさがる!
~VOC活動のせいで他部門とギスギス度高まって、気持ちがいじけることあるよねえ~
(※出典:青春出版社刊『クレーム対応のプロが教える心を疲れさせない技術』)
社長が『顧客満足向上』のスローガンの全社的な徹底を掲げた5年前にから、わがお客様相談室は、クレーム対応専門部門ではなくなり、お客様の声をまとめあげ関連部門や上層部にその分析結果を定期的に提示する作業も担当することになった。
毎日、本日発生したクレームをキーワードに加工し、社内配信。週1回、今週の発生クレームの多いものを順番にまとめる加工をし、社内配信。これは重役にも配信する。さらに月に1回、今月の発生クレームの要因や、お客様の声から拾い上げた、自社への期待や商品への期待をまとめ、分析加工し、社長、重役をはじめ社内全域に配信する。
実のところ、その作業量たるや想像を絶するものだが、この分析から見て取れる改善点にすぐさま、しかるべき部門が取り組み、2~3ヶ月後には改善されたリニュアル商品が店頭に並ぶなら、こんな苦労もなんのそのという思いでやっている。
でも、さらなる本音は、「本当に、社内の人、見てくれてるのかなあ。」「そもそも、社長にも配信しているけれど見てくれてるのかなあ。あんまり反応ないけど。」「あんまり、これらの分析結果を見て、担当部門がバタバタと改善に走ってくれている感じ、ちっとも感じないけど、行動起こしてくれてるのかなあ。」
そんな疑惑が日々積み重なっていくほどに、「こんな仕事でいいのかなあ。」なんて自分の存在価値を疑うようになり、「この仕事なくてもいいんじゃないのかなあ。」なんてこの仕事の存在自体に意味を見出せなくなる。
先日も商品開発会議で、「お客様から、もう少し、開口部を大きくしてほしいとのお声が多いので、検討をお願いします。」とひとこと言ったところで、「今の売価が上がっても営業がいいって言うならできますよ。」と担当部署の責任者が営業にその判断をゆだねる動きをし、その声を受けて、営業の誰もがうつむき加減でくぐもった声で「値上げは困ります。」と言ったような言わなかったような。でも明らかに「値上げは困る」というオーラを出しながら、目線をそらしていた。
担当重役たちも、うなるばかりでこれといって、キレのある発言をしようとしない。
それならもう『顧客満足向上』『お客様の声を商品に反映しよう』なんて、大げさに掲げなくていいんじゃないの?実際、会社の中では誰も積極的にそれに取り組んでいるようには見えない。この頃は「社長も言いっぱなしジャン。」って言いたくなる自分の気持ちを、自分で見ないようにするのに苦労する。 「できないならできないでいいんじゃないの。」と、口先だけのスローガンを消去したくなる。
その改善にはコストがかかるとか時間がかかるとか、いろんな調整が必要だとか言いながら本当は面倒くさいからそういうこともわかっている。
だけど、お客様の声には知らん顔もできないほど感心するものもある。自分が消費者だったらもっともだと相づちをたっぷり打ちたくなることもたくさんある。
会社の中で、消費者の声から遠い役割の部門は当然のこと、消費者の生の声から単に距離的に、遠い場所で仕事をしている部門になればなるほど、『お客様の声を商品に反映する』のを面倒くさがる傾向にある。単純な現象だけど不思議な現象。それで言うと社長や重役もお客様の思いをそのままの温度で感じていないんだろうと無駄な期待はしないように自分を納得させる。
そんな中で、確実に進んでいるのは、他部門との目に見えないコミュニケーションの溝の深さ。こちらから発信したものへのフイードバックのレスポンスが額実に遅くなっているし、2回は催促しないと帰って来ない。帰ってきた内容も、「返せと言ったので、返せばいいんだろう。ほら、返したよ。」というやけっぱちの思いが行間にあふれていて疲れる。
ついつい、消費者を恨みたくなってくる。『企業は消費者の声に応えて、改善や、開発するのが当然。』と思っているけれど、それはそうなんだけれど、でも『どこの企業もそうしているんでしょう!』と信じているならそれはまちがい。
そのために、企業の一人ひとりの担当者は、こんなに社内で戦っているんだ。
『お客様の声を商品に反映する』ということは一筋縄ではいくことではないんだ。簡単なことではないんだ。ということを知っていますか?
この現実を、消費者と社長は解っているんだろうかと日に日に気持ちがいじけていく。
でももし、もし、一人のお客様が「この間、電話で指摘したこと、今日、久しぶりにその商品買ってみたら、改善されていましたねえ。うれしかったわ。ありがとう。本当に取り組んでくれて。」なんて言って来てくれることがあったらどんなに嬉しいだろうと思うと、今日もこの仕事をおろそかにできない気持ちにかられる。
私が説得しなければならないのは、お客様ではなく、社内の人たちであることに納得がいかないものはあるけれど、この人たちともいつかツーカーのコミュニケーションがとれるようになり、お客様からもお礼を言われる日が来ることを楽しみにしながら、今日もエクセルを前にキーボードを叩いている。
お客様の声を反映するVOCの鍵をにぎっているのはお客様の生の声を聞いた人
お客様の声を商品やサービスに反映する活動は、ISOの普及により、取り組み企業がふえ、今ではISO取得を考えていない企業でも当然のこととなりつつあります。
購入したお客様が商品の改善部分指摘し、企業はその指摘に則ってすぐに改善に取り組み、より消費者の満足度の高い商品を市場に放つという善循環は、素晴らしい消費構造ではあるけれど、思いのよらない問題が各企業に小さく立ちはだかっていたのです。
お客様の声を商品やサービスに反映する意識の高さは、お客様の生の声から遠のけば遠のくほど、低くなり、相変わらずお客様の生の声に最も近いところで仕事をしている担当者たちが、その業務に一向に充実感や、達成感を感じることができない現実が横たわっているのです。
お客様の声を重要視するあまり、極端な表現をすれば会社の中で孤立してゆくという現象が発生しています。