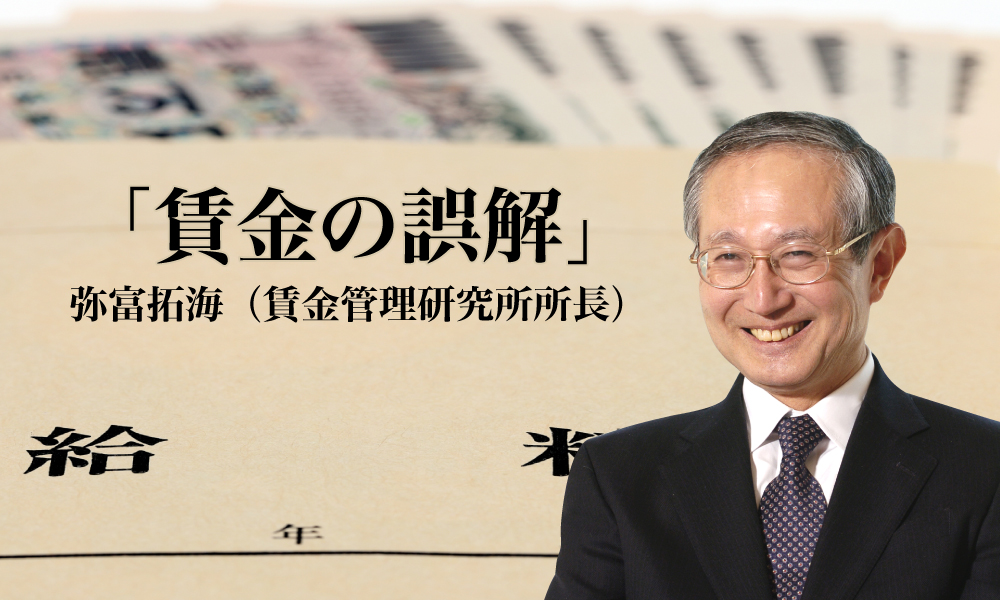労働基準法第32条では「使用者は労働者に1週間について40時間を越えて労働させてはならない」「1週間の各日については、休憩時間を除き1日について8時間を越えて労働させてはならない」と定めています。これが法定労働時間であり、法律で定められた労働時間の限度です。
もしも、この法定労働時間を超える就労(時間外および休日勤務)が欠かせない時には労使による36協定が必要であり、割増賃金の支払いと時間外、休日勤務それぞれの割増率が法律で定められています。
一方、企業には就業規則があり、月例給与の根拠となる始業時刻から終業時刻までの拘束時間が示され、一日の就業時間が定められています。
(1)始業8時30分 (2)終業17時30分 (3)休憩12時00分より13時00分
上記のように、就業規則に時刻が定められているとすれば、この会社の所定内勤務は1日8時間であり、加えて月の就労日数が平均で21日とすれば、これが月々定めて支払われる所定内給与の根拠となります。
この就業規則で定められた所定内勤務が通常勤務であり、この就労時間を越える時間外、休日勤務は超過勤務です。
労基法第37条には時間外、休日及び深夜の割り増し賃金が定められており、超過勤務がある場合には所定内給与金額をひと月の所定労働時間数で除して時給を計算し、割増率を乗じた割増時給額に該当時間数を掛けて割増賃金を計算し、支払わなければならないと定めています。
先日、諸手当の種類が多い会社に伺いました。その手当金額の月例給与に占める割合はなんと35%(労務行政の調査では通常15%以下)でした。なぜ手当の種類と金額を多くしているのか、その理由を伺ったところ、「基本給の割合が多きければ、それだけ残業手当の金額が増えてしまうから」と答えが返ってきました。しかしこれは間違いです。
なぜ間違いかと言えば、割増賃金の基礎となる賃金は基本給だけではなく、労基法第37条第5項及び同法施行規則第21条に限定列挙されている賃金((1)家族手当、(2)通勤手当、(3)別居手当、(4)子女教育手当、(5)一定条件を充たした住宅手当、(6)臨時に支払われる賃金、(7)1ヵ月を超えて期間ごとに支払われる賃金)のいずれにも該当しない(各社で定める)手当はすべて割増時給額の算定に加えなければならないのです。
上記のように手当の種類と金額の多い企業は、月例給与の支給総額では遜色なくても、基本給額は同業他社や世間水準と比べて見劣りしてしまいます。それでは優れた人材の採用も、定着も難しくなります。不要な手当は廃止し、制度として欠かせない最低限度の手当を残し、基本給の充実を考えるべきです。