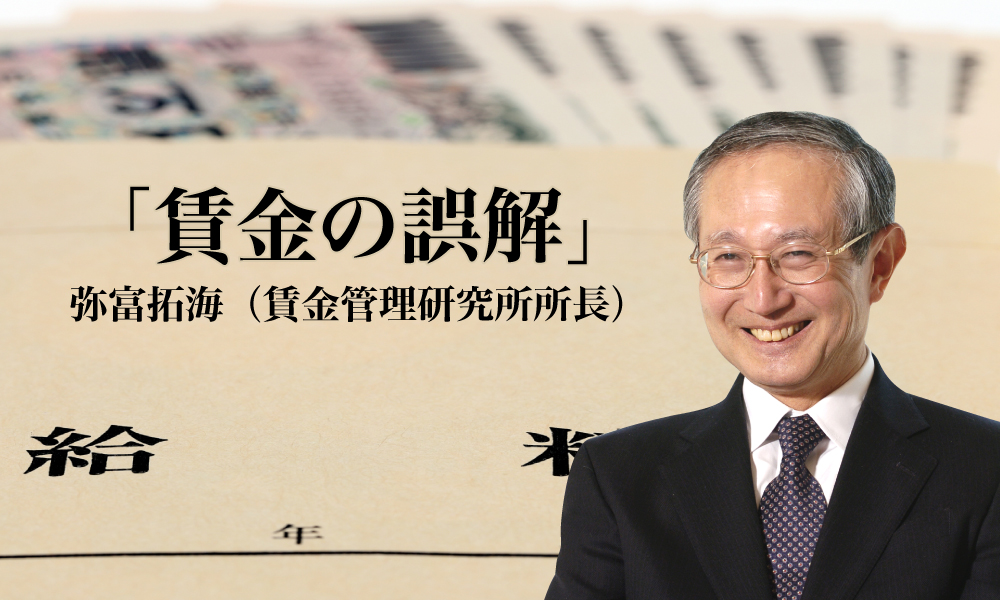- ホーム
- 指導者たる者かくあるべし
- 逆転の発想(42) 現実を理想と融合させるのが政治家の任務である(南原繁・東大総長)
単独講和か全面講和か
発足後間もない菅義偉政権は、日本学術会議の会員候補6人の任命拒否問題をめぐり批判にさらされている。一般国民にとっては遠い世界の問題に見えるが、反対意見を可能な限り封じ込めたいという意思は政治リーダーのみならずあらゆる組織指導者にとっての宿痾(しゅくあ)のようなものである。
1950年、吉田茂は独立に向けての総仕上げである先の大戦の講和問題について取り組んでいた。米ソ両大国の冷戦情況を受けて、ソ連を含めての全面講和か、米国など自由主義陣営との単独講和かをめぐって世論は二分していた。
独立を優先目標とする吉田はソ連封じ込め作業を進める米国との間で単独講和のシナリオ作りを進めていた。「講和条件に難癖をつけるソ連との交渉決着を待っていては、独立はいつになるかわからない」というのが、吉田の思いだ。これに公然と否を唱えたのが東大総長であった南原繁(なんばら・しげる)だった。
吉田茂の「曲学阿世の徒(きょくがくあせいのと)」発言
南原は米国に乗り込み全面講和論を主張し、吉田の神経を逆撫でする。さらに東大卒業式においても全面講和を説いた。
これに対して吉田は、与党自由党の両院議員総会で演説し、「永世中立とか全面講和などということは言うべくして行われない。それを南原総長は政治家の領域に立ち入りあれこれ言うことは、曲学阿世の徒に他ならない」と口を極めて批判した。
「曲学阿世の徒」とは『史記』に登場する言葉で、〈真理を曲げて、世間や時勢に迎合する言動をすること〉を意味する。学者に対する最大の侮辱だ。「現実政治を知らない学者風情は黙っておれ」という喧嘩の売り言葉である。
南原は、戦前の言論弾圧の歴史を例に引き、「学問の冒涜(ぼうとく)、学者に対する権力的弾圧以外のものではない。国民の覚悟を論ずるのは政治学者としての私の責務である」と受けて立った。そして言う。
「複雑変移する国際情勢において、現実を理想に近接融合させるために、英知と努力をかたむけることにこそ、政治家と政治の任務がある」
そして「曲学阿世の徒」の一言で批判を封じることにこそ「日本の民主政治の危機がある」と刃を突きつける。政治のトップと学者のトップとの論争に世論は沸騰した。
菅政権の過ち
考えてみれば、南原の言う〈現実を理想に近接融合させること〉こそ、吉田政治の信条であった。連合国の占領下で権力を半ば奪われた中で、憲法改正、講和と米国に振り回される現実のもとで国家の自主性、独立という理想に向けて奮闘していた。痛いところを突かれたのである。
政治的主張は異なってはいても、吉田、南原ともに講和に対する考えを国民の前に堂々と主張し説明した。これが民主主義である。
ひるがえって日本学術会議問題を考える。首相をはじめ菅政権は、法律的任命権を盾に「任命拒否の法的正統性」をいうばかりで、6人の学者を任命拒否した理由を説明しないままである。政権の権力は強大である。与えられた人事権を振り回しているだけではリーダーの責任を果たしたとは言えない。説明責任を果たすべきである。
任命拒否したからには理由がある。公安・警察官僚が任命拒否リストを作成した背景がおぼろげながら明るみに出るに至り、安保関連法制をめぐる反対論者を外したことは誰の目にも明らかである。ならば、きちんと理由を明らかにすべきである。そこから論争をはじめるべきである。
権力を握るリーダーは、ともすれば、批判世論をうるさく感じる。批判者を切って捨てることは簡単だが、それは思い上がりであり、批判を強引に封じた組織は結局、衰退する。
トップが欲しいままに人事権を行使し、その説明をせずに批判を封じる会社があったとしよう。だれもそんな会社で働きたいとは思わない。嫌々トップの顔色を見ながら働く忖度社員ばかりになる。そんな組織に未来はないのだ。
(書き手)宇惠一郎 ueichi@nifty.com
※参考文献
『戦後日本政治史Ⅳ』信夫清三郎著 勁草書房
『回想10年(1)』吉田茂著 中公文庫
『マッカーサーと吉田茂 上、下』リチャード・B・フィン著 内田健三監訳 角川文庫