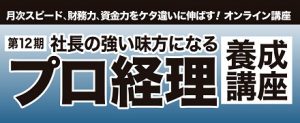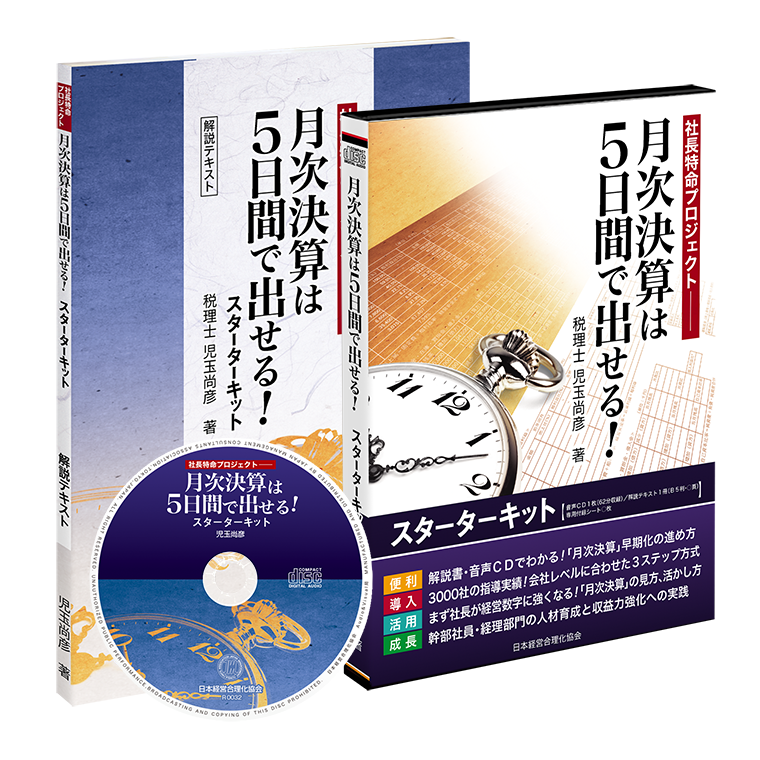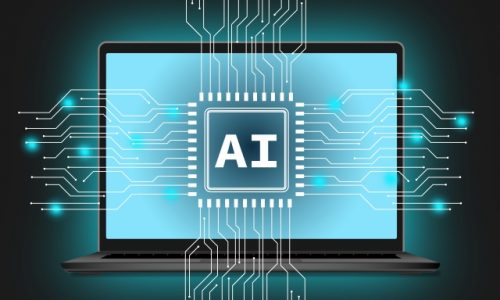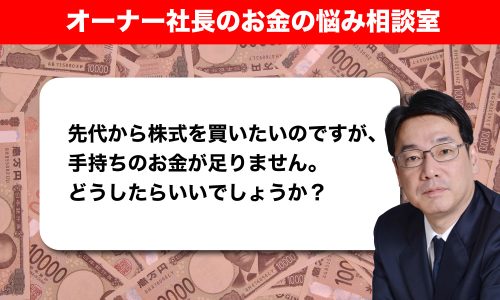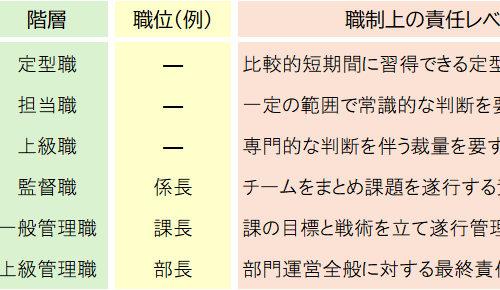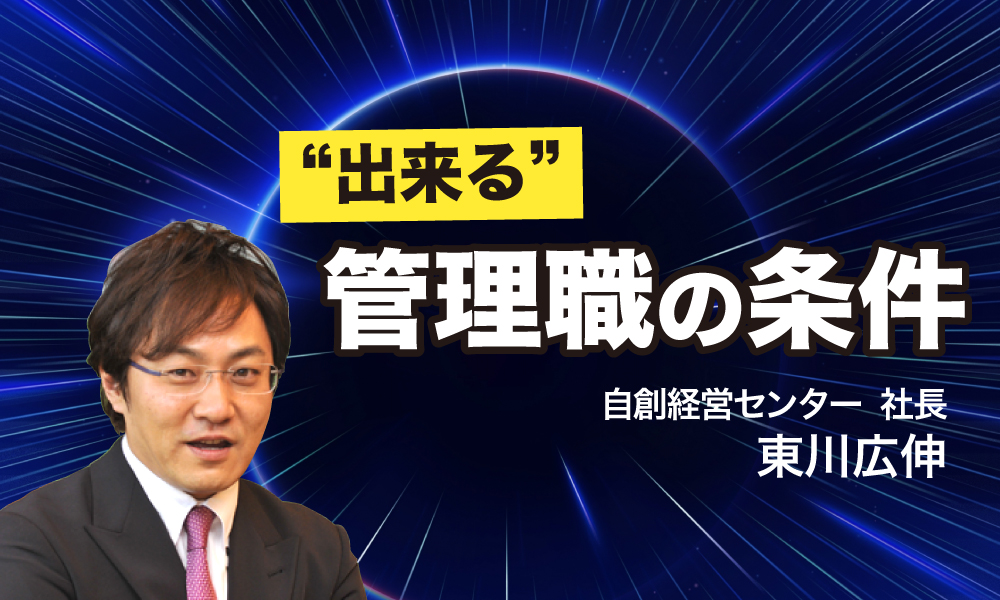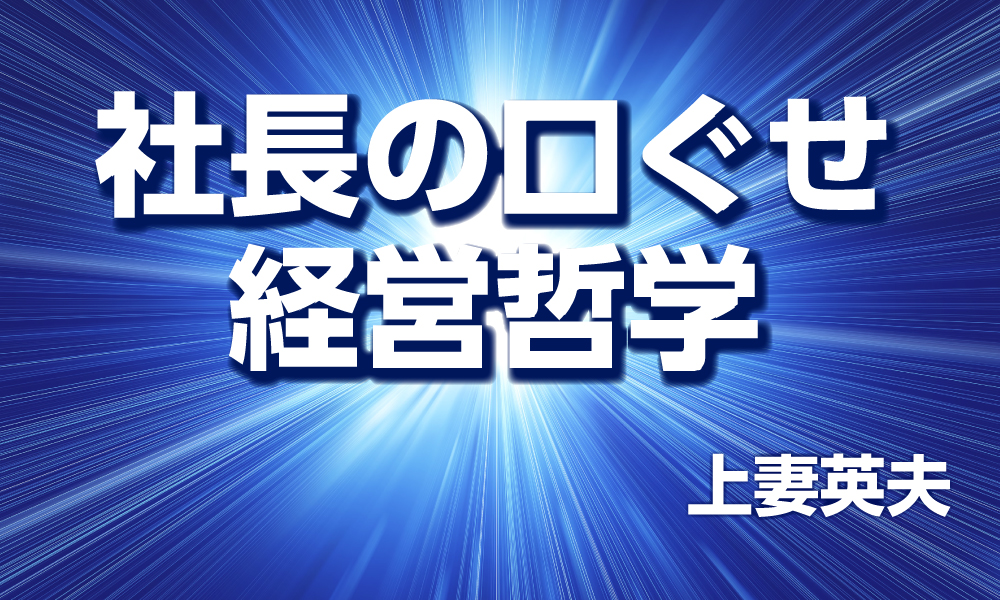コロナ禍でテレワークや在宅勤務が推奨されるなか、企業では書類のペーパーレス化が進んでいます。印刷、押印して郵送していた請求書や領収書などの紙の書類は、Eメールに添付して送受信する方法に変わりつつあります。
そこで今回は、請求書や領収書をペーパーレス化するときの経理処理上の注意点について説明します。
請求書や領収書等の電子化については、第6回のコラムでも説明しています。そちらも参考にしてください。
◎「第6回 契約書・請求書の電子化を始めていますか?」 https://www.jmca.jp/column/kodama/kodama-006-2009.html
御社では、毎月受け取る請求書の何%がペーパーレスですか?
中小企業でも進む「電子取引」
事業者が発行する請求書や領収書を紙ではなく、インターネット等を介して電子的にやり取りする方式のことを税法上「電子取引」といいます。
具体的には次のような取引が電子取引に該当します。
(1) 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
(2) ウエブサイトのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)、又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用
(3) クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
多くの人が日常的に利用している取引がほとんどです。
2020年10月に「電子帳簿保存法」が改正されました。紙の保存義務がなくなり、電子取引では電子データのまま保存することが認められるように変わりました。企業のペーパーレス化はさらに普及するでしょう。
実際に中小企業でも、見積書や請求書等をEメールで送受信している会社は増えつつあります。会社でもインターネットの通販サイトで商品を購入して、クレジットカードで決済していることでしょう。
社員は交通系ICカードを使っています。これらもみな、電子取引を利用していることになります。
また、電子取引は印紙税法上の課税文書に該当しないため、印紙を貼る必要がありません(紙がないので貼れません)。印紙代の節約を目的にして、領収書等のペーパーレス化に取り組んでいる会社もあります。
請求書の発行を電子取引に移行した会社では、自社の事務作業時間が削減できただけでなく、得意先の業務効率の向上にも貢献しています。
御社では、紙の書類の作業に毎月どのくらいのコストをかけていますか?
2022年1月からは電子取引のデータ保存が必須になる
電子取引に関して規定しているのが「電子帳簿保存法」です。請求書や領収書を、電子的に受け取ったり、送ったり、保管するときのルールが決められています。
特に、実務を担当する経理社員は、電子取引の管理について注意が必要です。
まず、電子取引にはタイムスタンプ(時刻認証機関が発行)を付与するか、データに修正や削除が行われないような規定を作って運用しなければなりません。
これに加えて2022年1月からは、原本の電子データの保存が義務付けられます。
2021年12月までは電子取引を紙の書類に印刷して保存することが認められていますが、2022年1月からは電子取引は電子データ形式での保存が必要となるのです。
さらに、保管した電子取引を税務調査の時に、取引日、取引先、金額によって検索できるようにしておくことも要件になっています。
以上のように、電子取引のデータは決まったルールで保管しなければなりません。
経理社員がこれまで紙の請求書や領収書を整理分類して保存してきたように、電子取引のデータについても管理が必要になるということです。
この電子取引の管理ができていないと、最悪の場合では、青色申告が取り消されることにもなりかねません。ですから、今年中(2021年)にしっかりと準備をしておく必要があります。
御社の経理は、電子取引の管理ができていますか?
書類のペーパーレス化は避けられない
企業は事務処理効率の向上や、テレワーク・在宅勤務の推進に向けて、ペーパーレス化を今後もさらに進めていくことでしょう。
一方で、2022年1月からは「電子帳簿保存法」が改正されて、電子取引の管理方法が厳格になっていきます。当分の間は、紙の書類と電子取引が併存することになり、経理事務が煩雑になることは確実です。
だからといって、自社の経理だけ電子取引を受け入れずに、今までどおりすべて紙の書類で管理し続けることは難しいでしょう。
得意先からは、「当社はペーパーレスにしていますので、請求書をEメールで今日中に送ってください」と言われます。
仕入れ先や外部発注先からは、「請求書を添付しましたので確認願います。領収書が必要な場合はPDFで送ります」というメールが届きます。
経済活動のペーパーレスの流れには逆らえません。自社だけ、紙の書類で事務管理をしようとするのは不可能です。
御社は、いつから請求書や領収書をペーパーレス化しますか?
2021年中に電子取引の対応準備を済ませておく
電子取引の管理方式については、ほとんどの会社がこれから実務対応を検討して、2021年末までに準備することになります。会計システムや販売システム、クラウドサービスについても、「電子帳簿保存法」の改正対応が必要になります。早い時期に、「電子帳簿保存法」の改正について顧問税理士から説明を受けるとともに、ペーパーレス後の税務調査の対応を相談してください。
社長としては、経理の細かい部分まで指示する必要はありません。しかし、会社が取引している電子取引の状況について把握して、今後の対応方針を決定しておきましょう。そして、経理社員に指示して、社内の電子取引の管理体制を準備するように促してください。
御社のペーパーレス化の方針は、全社員に伝わっていますか?
【参考】
国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」令和3年7月
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_06.pdf
ー - - - - - - - - -
【講師セミナーのお知らせ】
2021年9月3日(金)開講【全4回】
月次スピード、財務力、資金力をケタ違いに伸ばす!オンライン講座
第12期・社長の強い味方になる「プロ経理 養成講座」
児玉尚彦(プロ経理育成コンサルタント)
形式:オンライン講座
*全講、16時半から個別指導の時間を設置。会期中の決算業務、月次、事務処理……社内実務に並走しながら、円滑に最先端の経理実務を落とし込んでいただけるようフォローします。
▼ 詳しくは日本経営合理化協会サイトをご覧くださいませ https://www.jmca.jp/semi/S214459