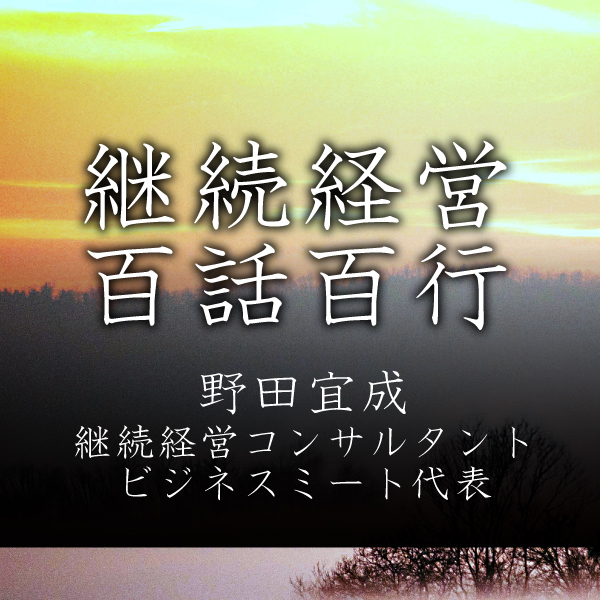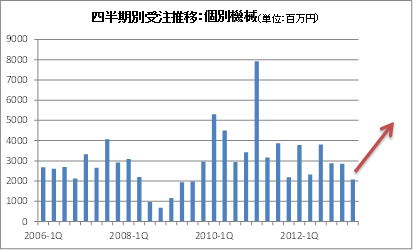今年も暑い夏がやってきました。
私事で恐縮ですが35年前の今頃は、真夏の最中にリクルートスーツを着て、就職活動をしていました。ある会社の採用面接で好きな本はと尋ねられ、城山三郎著「官僚たちの夏」と答えたことを今も覚えています。真夏の日盛り頃の都心の印象とも相俟って、このタイトルが強く印象に残っているのかもしれません。
1950年代から60年代にかけての高度成長時代を生きる通産官僚の姿を描いた経済小説ですが、主人公で後に通産次官となる風越やその腹心である鮎川や庭野が「無定量無際限」に働く姿に、私もその時代の息吹とダイナミズムを感じたものです。もちろんそこに描かれている官僚たちの働き方は、今の時代であれば時代錯誤の「ブラック企業(職場)」と一言の下に否定されるべきものでしょうが、社会人になる前の私には、その物語のなかに圧倒されるような仕事への熱量を感じたものでした。官僚のみならず民間企業においても同様の働き方が肯定されていたように思えます。「経済成長や組織拡大とともに仕事の範囲も広がり、所定労働時間の枠にも囚われない。」そうした働き方に対して、当時は疑問を感じることはありませんでした。
時は移り2021年の今、人材の多様化(ダイバーシティ)が求められる時代となり、昨年4月に施行された働き方改革法では、労働時間管理の適正化と均等待遇・均衡待遇(いわゆる同一労働同一賃金)の実現が企業に求められるようになりました。
過去の労働事情に照らして考えると、戦後70年以上にわたって仕事の範囲や労働時間に関して「無限定の正社員」を中心に築きあげられた雇用慣行を、限定的な働き方を広く認めてより多くの人に労働市場に参加してもらえる雇用環境へと転換していこうという一連の流れがよくわかります。
経団連は、経営労働政策特別委員会報告の中で、日本独自の「メンバーシップ型雇用」のメリットを生かしつつも、時代に合わない部分は「ジョブ型雇用」の導入で、自社型雇用システムを確立することを提言しています。職務記述書で職務範囲を明確に定めた「ジョブ型」の導入も「限定的な働き方の正社員」を広く認めようという動きの一環として捉えられます。
労働時間、働く場所や地域、職務内容、責任範囲等々、様々な切り口で限定的な働き方を認めるということは、まさに多様化(ダイバーシティ)の実現そのものといえましょう。8年ほど前から「限定正社員」(地域限定ではなく、仕事範囲や労働時間を限定した正社員という意味で)という言葉が人事労務の世界で広く使われるようになりましたが、これも従来の正社員の仕事範囲や労働時間が限定的でないことへのアンチテーゼなのだと考えると、わかりやすいかもしれません。
いずれにしても今の時代に求められる変革は、大手企業よりむしろ中小企業にとって重要な意味を持つと思われます。なぜなら、背景にある圧倒的な人材不足の影響を受けるのは主に中小企業であり、これからの5年、10年の人事対応が20年先、30年先を左右すると考えられるからです。