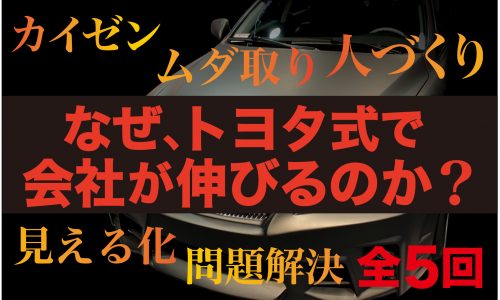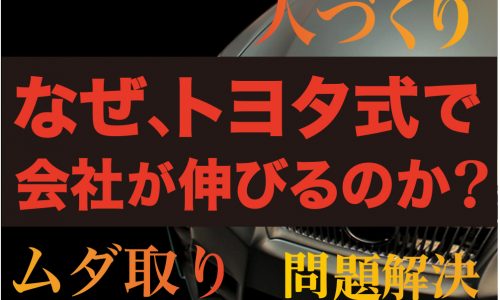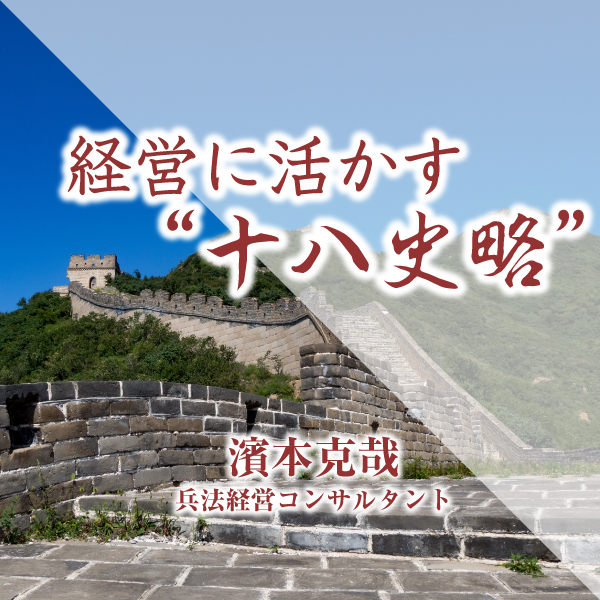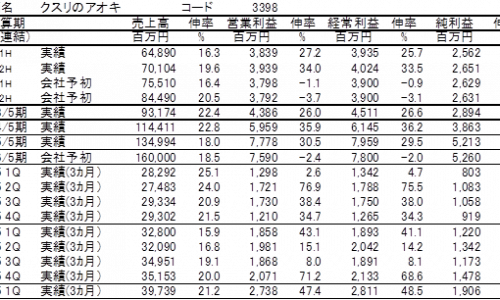新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。私は毎年高尾山薬王院に初詣に行くのですが、今年もみんなでいい改善を実行し、いい年になるようにお祈りしました。
●薬王院には、今年も参拝客がたくさんいました。

さて、昨年末の冬休みに入る直前、私は次のように考えました。2009年はとても大変な年だった。2010年もその延長線上の年だからやはり大変な年だろう。
しかし、どんなに大変であるかをいくら考えても意味がない。そうではなくて、どんな手を打ってこの難局を乗り切るかを具体的に考えなければいけない。
そこまでは思いついたのですが、では具体的にどのような方法で考えるかで行き詰りました。うーうー困っていたときに、孔子の言葉として、次の文章にめぐり合いました。
「子曰。吾嘗終日不食。終夜不寝。以思無益。不如學也。」(子曰く、吾(われ)かって終日食わず、終日寝ずして、もって思うも益なし。学ぶに如かず。) (論語 衛霊公 第15-30)
漢文は苦手中の苦手であったはずなのですが、なぜかその時は、この文章が心に響きました。「どんなに一人で考えていてもダメですよ。昔の偉人の言ったことを学びなさい。」と孔子先生にアドバイスされた気がしました。
そこでこの冬休みは過去の偉人の本を読もうと決めて、アメリカのフォードの創業者であるヘンリー・フォードが書いた「藁(わら)のハンドル」(中公文庫 竹村健一訳 原題は “Today and Tomorrow” )を読みました。
そして驚きました。1926年に書かれた本ですから既に80年以上前の本なのですが、書かれたばかりの本なのではないかと思うほど、テーマが現在の問題と通じていて、それらに対してきわめて鋭い議論が展開されていました。
例えば、モノづくりの会社であっても「常に顧客のことを頭において、サービス精神を持って仕事をしなければいけない」とか、「金融業と社会改革の危険性」、あるいは「治療より予防が大事」といった、まさに今私たちが考えて解決しなければならないことが文中に語られていたのです。
本質を突いた議論は時代を超えるのだと気づかされました。私はこの本を読んで、表面的な変化に惑わされず本質的な改善を行いなさいと、フォード先生に指導されたように思いました。
以上、冬休みの報告をしてしまいましたが、私の今年の改善の抱負として書きました。このような切り口で皆様とご一緒に改善を進めてまいりたく存じます。今年一年、どうぞよろしくお願い申し上げます。
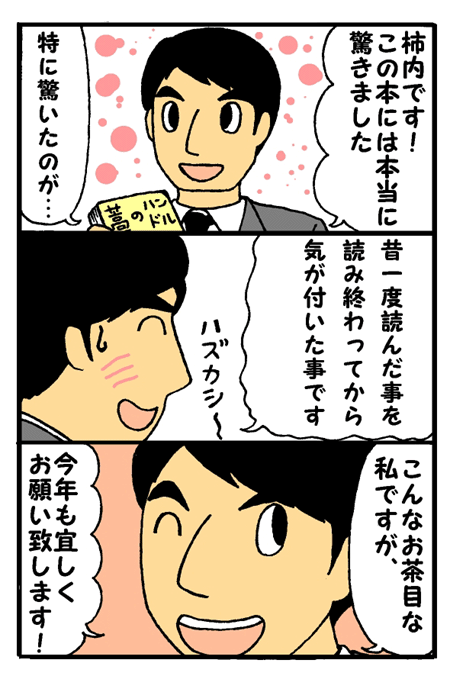
copyright yukichi
※柿内先生に質問のある方は、なんでも結構ですので下記にお寄せください。etsuko@jmca.net