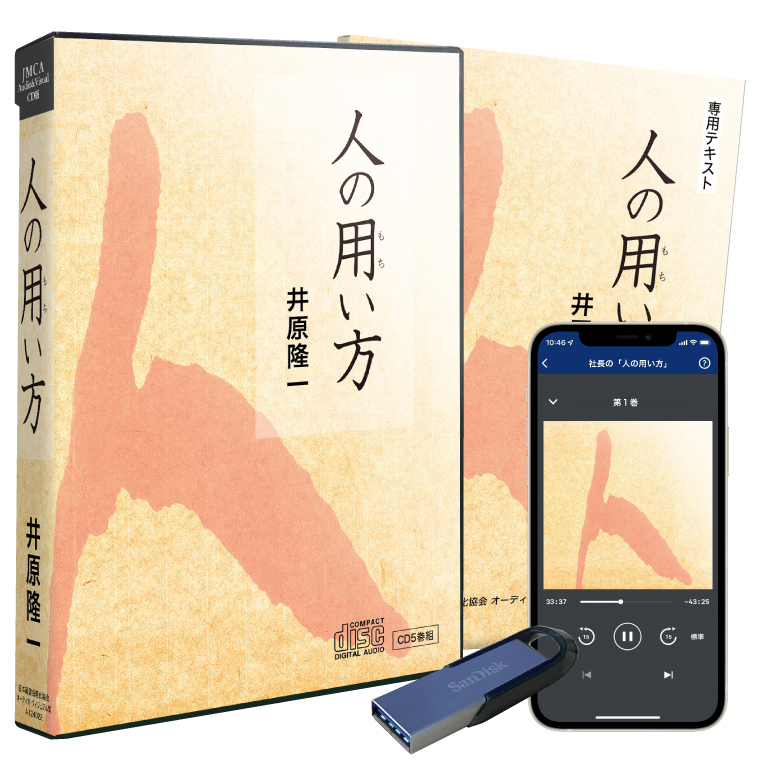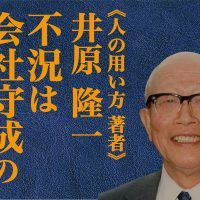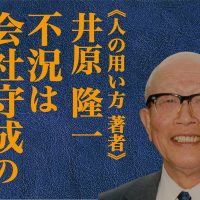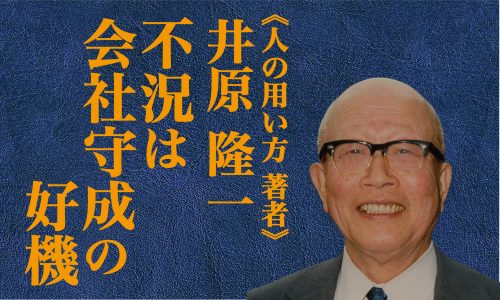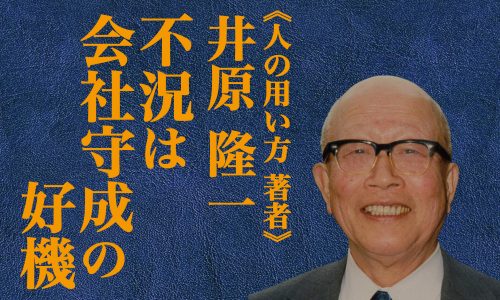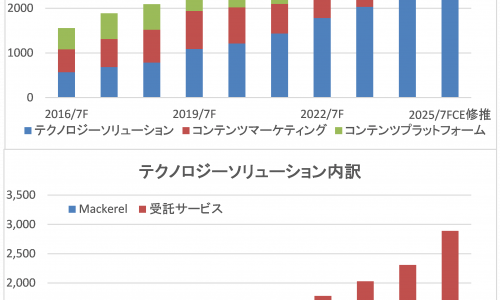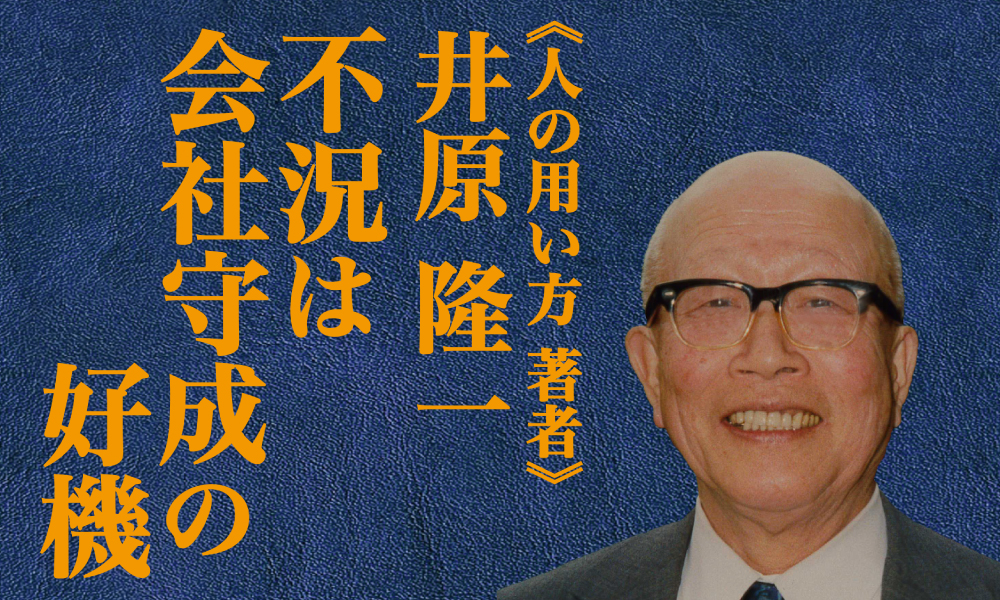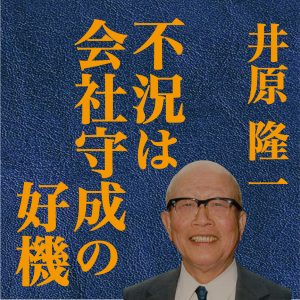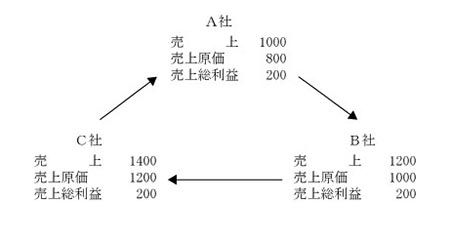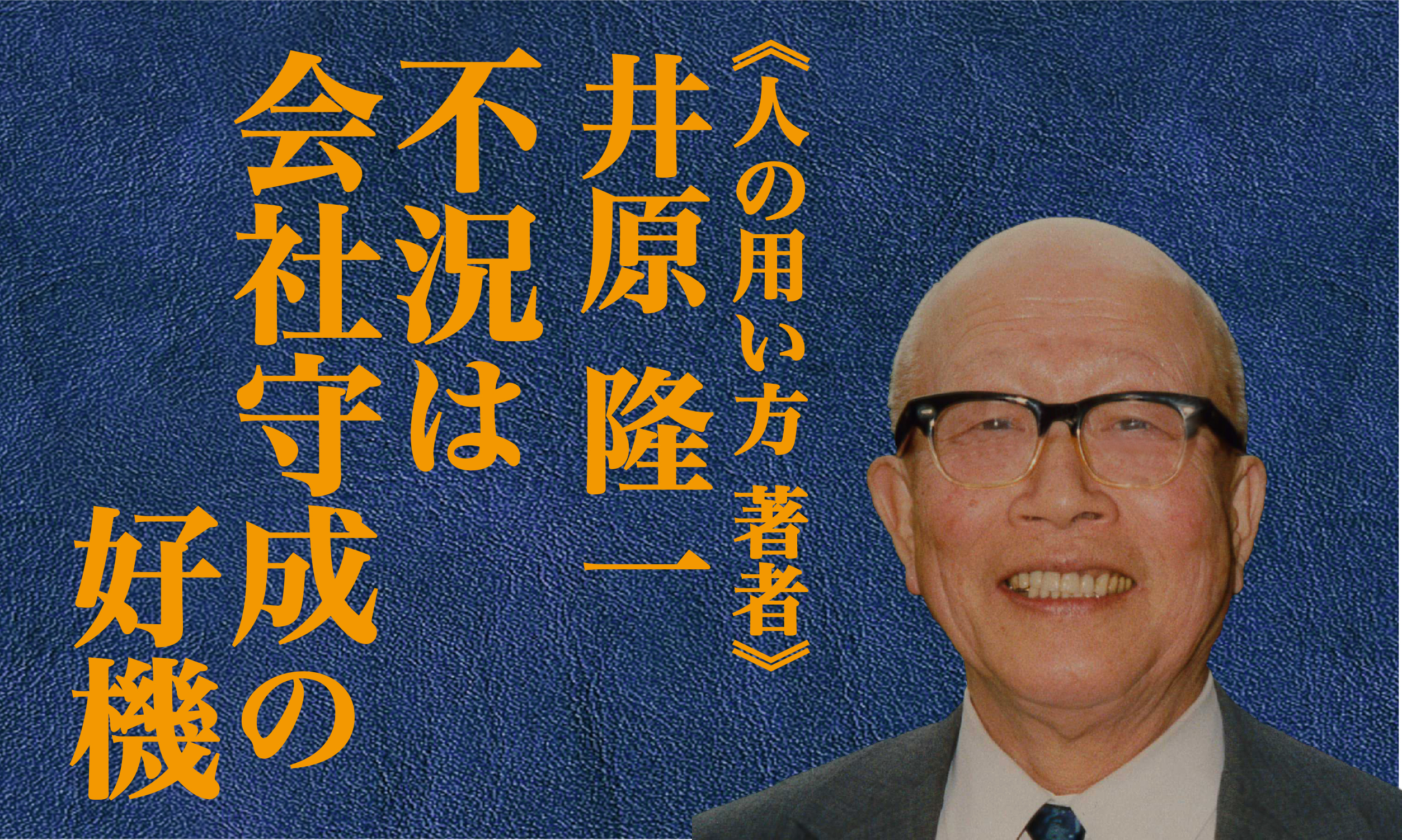 ※本コラムは2000年代に井原隆一氏が書き下ろした「不況は会社守成の好機」コラムを再連載するものです。
※本コラムは2000年代に井原隆一氏が書き下ろした「不況は会社守成の好機」コラムを再連載するものです。
西漢の祖 劉邦の三傑といわれた韓信が謀反のかどで主君劉邦に捕らえられたことがある。
その劉邦があるとき韓信に向かって諸将がどのくらいの兵の将になることができるかと尋ねた後で“自分はどのくらいの兵の将になれるだろうか”と尋ねた。
韓信は“陛下はせいぜい十万の将となるに過ぎないでしょう”と答えると“韓信、おまえなら何人の将になれるか”と聞かれ“わたしは多々益々弁ず。多ければ多いほど上手に使いこなします”
“多々益々弁ずる者がなぜ私の虜になったのか”これに対して韓信は、“陛下は兵士の将となることは不得手ですが、しかし将軍達の将となる力を持っておられます。これが私のとりこになった理由です。そのうえ陛下は
天がこの世に授けて人君とされた方で人間の力で人材となったのではありません”と
この漢の祖、劉邦を十八史略はこうのべている。“隆準にして龍顔、 美しゅ髯なり、左の股に七十二の黒子あり。寛仁にして人を愛す。意豁(いかつ)如たり、大度あり。家人の生涯を事とせず。(顔を鼻が高く、龍のような顔で、美しいあごひげが生えており、左のももに七十二のホクロがあり、性格は心が広く、情深く、人を愛し、気持ちがからりとしている)
また、呂公という人相をよく見る人からは“自分は人をよくみているが劉邦にまさる者はいない”。ついては、自分に一人の娘がいる、どうかそばにおいて掃除女に使ってくれと言われた。これが皇后の呂后である。
より多くの人の上に立つ条件を知ることができよう。
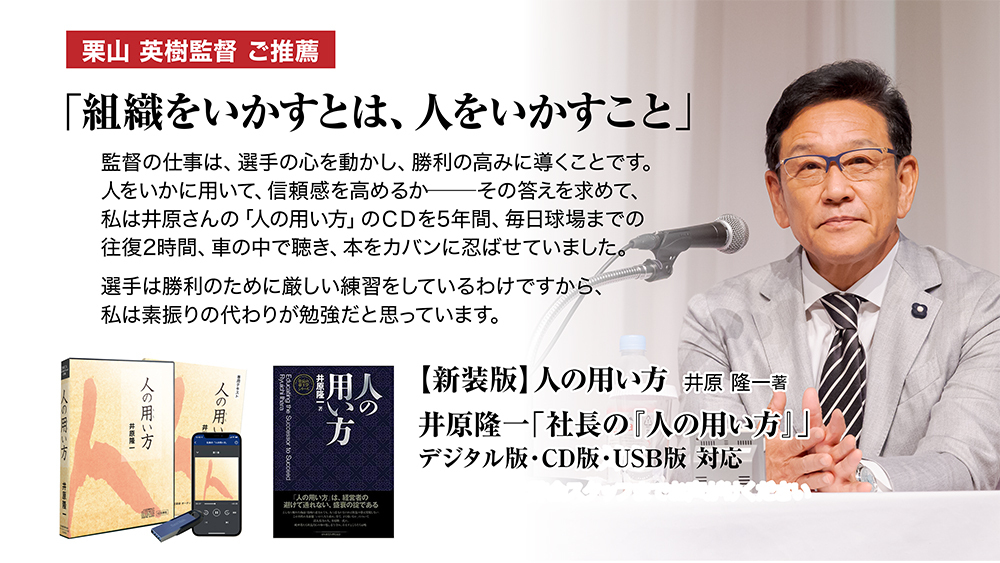
※栗山英樹氏から、本コラム井原隆一氏の「人の用い方」書籍と、井原隆一「人の用い方セミナー」収録講演CD版・デジタル版を推薦いただきました!
監督の仕事は、選手の心を動かし、勝利の高みに導くことです。人をいかに用いて、信頼感を高めるか―――
その答えを求めて、私は井原さんの「人の用い方」のCDを5年間、毎日球場までの往復2時間、車の中で聴き、本をカバンに忍ばせていました。選手は勝利のために厳しい練習をしているわけですから、私は素振りの代わりが勉強だと思っています。