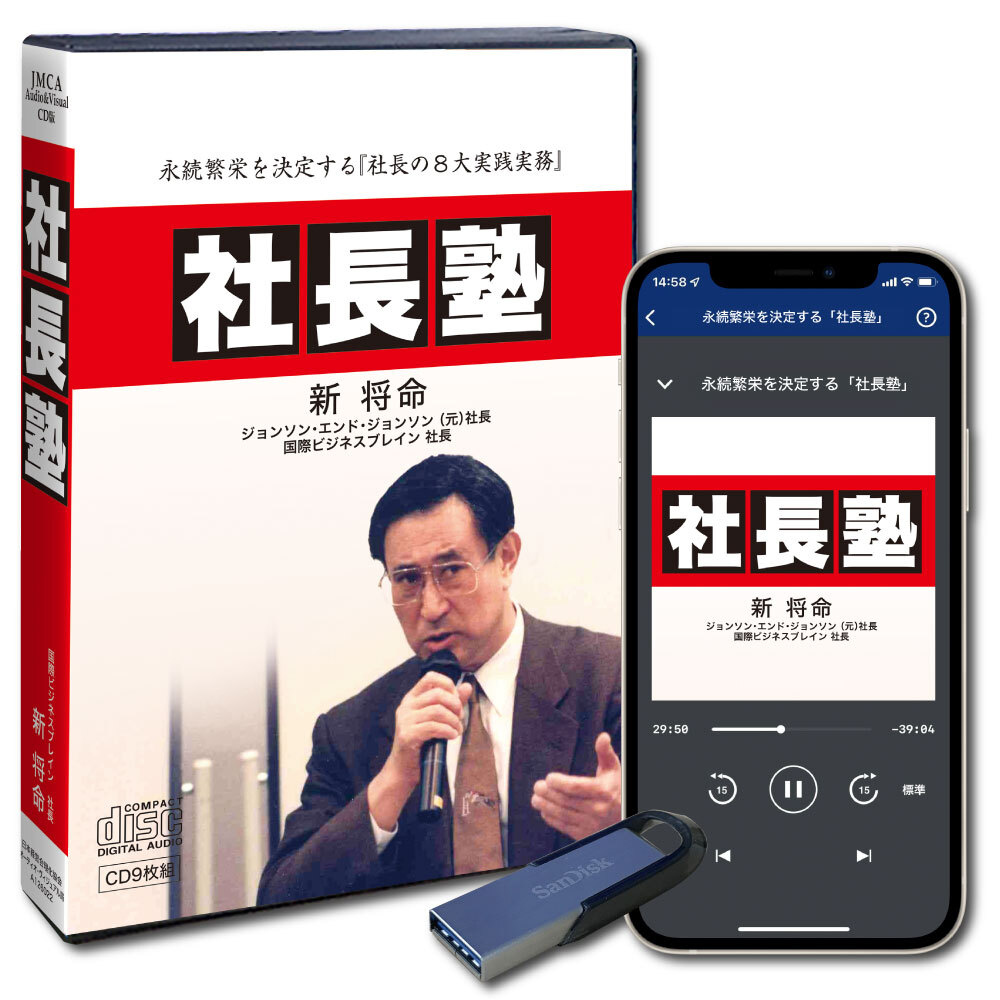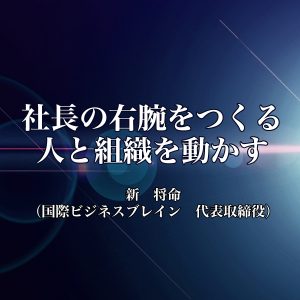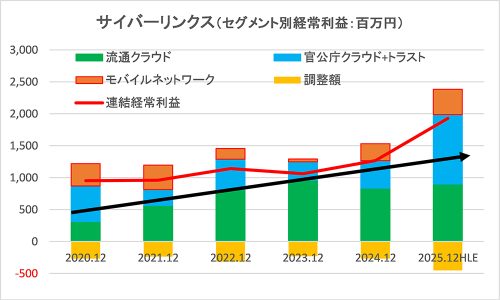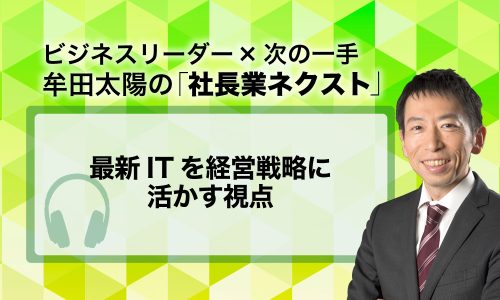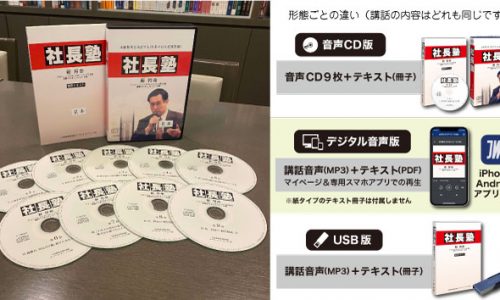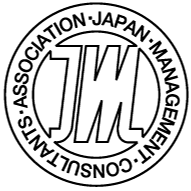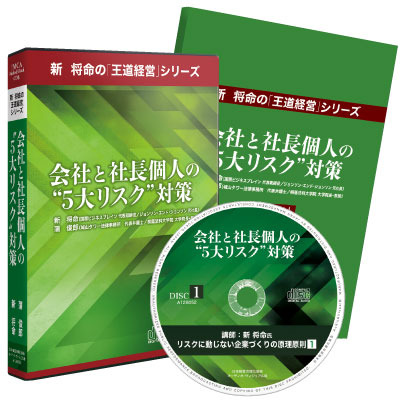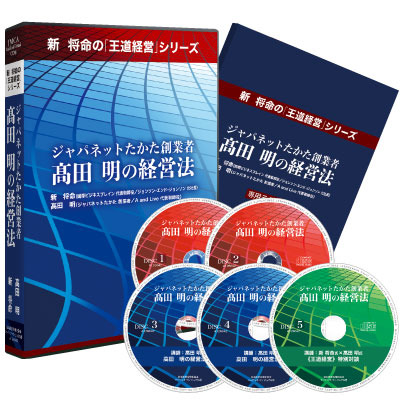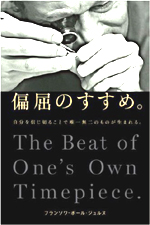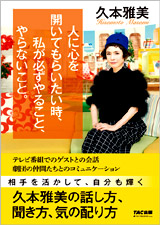スタッフの人員は“少なければ少ない方がいい(精鋭組織)”という考え方がある。
原則的には大賛成だが、これも程度の問題だ。
もちろん贅沢にスタッフを抱えればいいというものではないが、
質の良いスタッフであるならば、ある程度の予備軍の要素は、持てるならば持った方がいい。
なぜなら、何かトラブルが起こった時のために次のスタッフ・マネージャー候補の幅を広げることができ、
健全な競争を内部につくることができるようになる からだ。
加えて、スタッフの立場に立つ人へ「提案」を3つ。
(1)
とかく忘れがちになる点だが、スタッフ部門が常に念頭に置かなくてはならないのは、自分にとっての社内における
「お客様」、つまり“サービスを提供すべ き相手は誰か”ということである。それを忘れると、会社本来の目標・方針から
離れた志向や行動をする結果になってしまう。
(2)
スタッフ部門の人で、時々“ラインに対する命令権が無いこと”を理由に、欲求不満的な弁を漏らす人がいるが、
スタッフとは“直接の指示・命令権が無いに もかかわらずラインに影響を与える必要がある”のである。
したがって、スタッフの持たねばならない力は、論理性に基づいた説明力・説得力なのだ。
それだけに、スタッフであることは「説明力」を養うのによい機会でもある。
命令権なしに人を説得し動かすことができれば、権限があった時には、もっと人を動かすことができるはずである。
それゆえ、識見がない立場を嘆かず、むしろ「説得力」涵養のチャンスとばかりに積極利用するのが、賢明な態度であろう。
(3)
さらに、スタッフからみると、ラインは時折、「無理解・無計画・横暴・理不尽」に思われることをやる場合もあるが、それに
対して「論理性」という中味を 「人間性」というオブラートに包んで、こちらの考えを売り込むという能力を養う機会でもある。
いってみれば、女房が亭主から横車を押されたり、多少の無茶をいわれても、朝から晩まで汗水流して月給を稼いでくれる
ならば少々のコトは仕方ないとばか りに、結果的に巧く亭主を動かしてしまう操縦法にも似ている。
あわせて、ラインとスタッフは仕事の持ち分の分担の問題である。
それ以上でもそれ以下でもない。
“どちらが上位、どちらが偉いの…”という、小学校低学年的な議論だけはやめたいものである。
新 将命