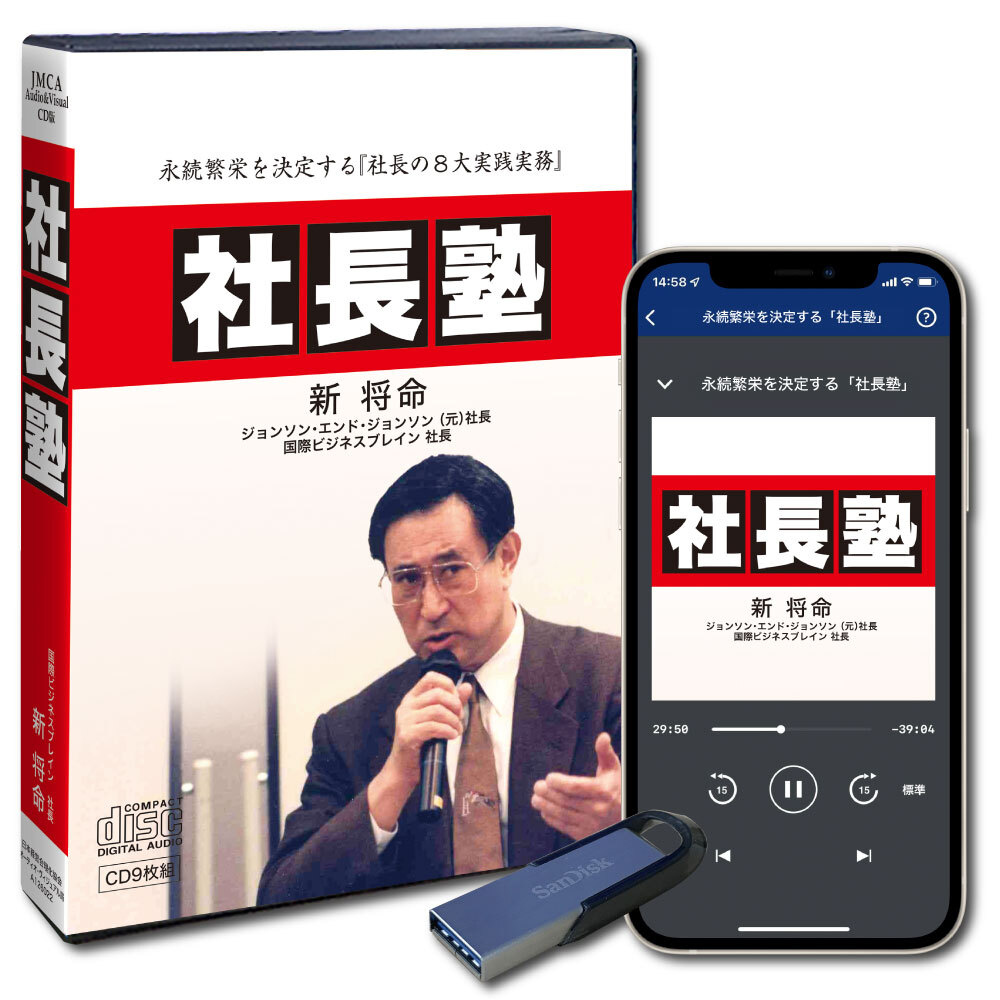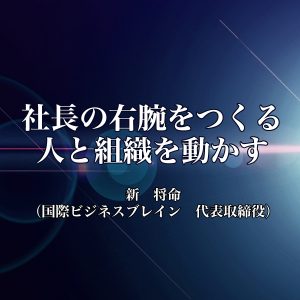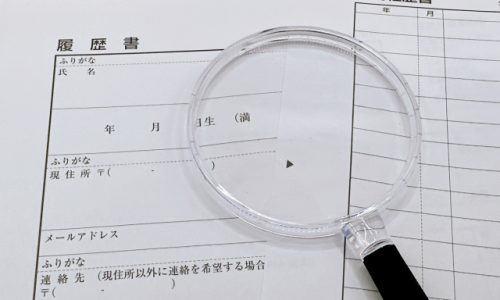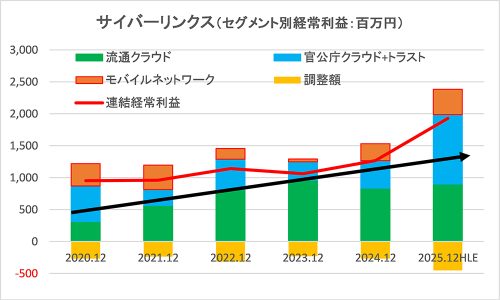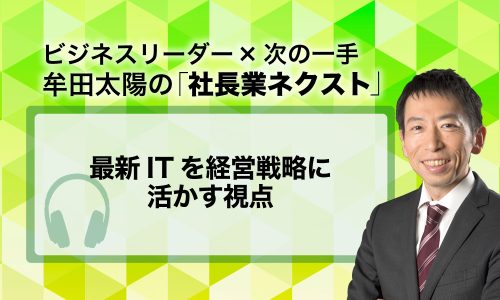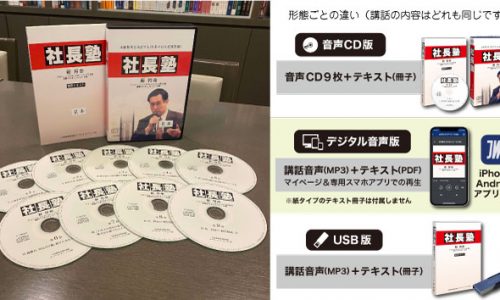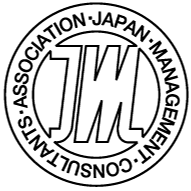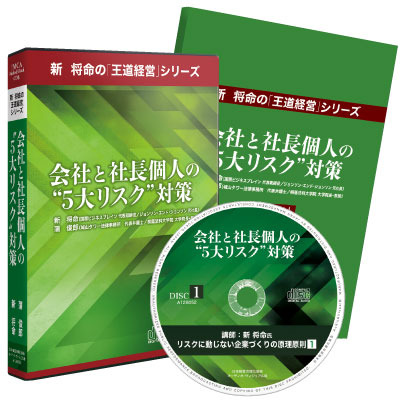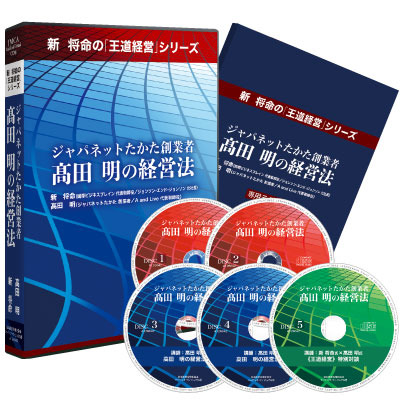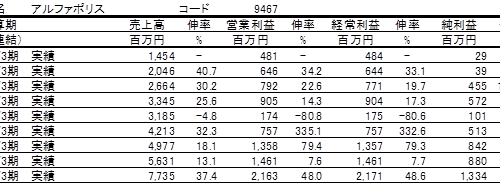問題解決能力の高い人というのは、マイナス感度が高いものだ。
といって、肯定論者を否定しているのではない。
“マイナスを見つけたからやめようではなく、マイナスをいかにプラスに変えるか”…その意欲が必要ということである。
日々発生する問題にいかに対応し、解決を図っていくかで、リーダーとしての資質が判断できるといっても過言ではない。
新しい時代のリーダーには「右手にコンセプト、左手にハウツー」が求められるが、
問題解決にあたっても、コンセプトとハウツーがある。
今回は、「コンセプト=発想」について考えてみたい。
1.問題は“あって当たり前”という発想を持て
会社の根幹を揺るがすような問題は別として、「健全な問題」はあった方が刺激になっていいともいえる。
一見、何の問題もな いという状況は、刺激が少なく、社内に淀(よどみ)が生じる原因ともなる。
そもそもの問題は、その人が「問題だ」と認識していなければ存在しない。
同じ現象や事実に接しても、物事の本質を見抜かな ければ、問題の本質は見えないものである。
2.肯定的な姿勢で問題に取り組むこと
「問題」を、ひとつの「良い機会」であると肯定的にとらえることである。
肯定的な発想でもののとらえ方を変えれば、アプ ローチする姿勢や結果も自然と変わってくる。
3.問題を早い段階で発見、摘出できる仕組み作りを進めること
何か問題が生じた時に、自分で解決しようとしない部下はいない。
しかし、早い段階で上司に問題の存在がわかっていれば、
自分の経験や知識、人脈などを使って、大きなトラブルになる前に解決できることも少なくない。
また、部下の育成のためにあえて問題にチャレンジさせるなど、教育のチャンスとすることもできる。
問題が発生した時に、その兆候が早く伝わるような組織の中の仕掛け作り、仕組み作りを心掛けたい。
4.問題追求の焦点を人ではなくその事象にあてること
部下が“会社のために”やったことで問題がおきた時には、
部下を責めるのではなく、仕組みや仕掛け、やり方を改善する、と いうとらえ方をする
5.問題解決そのものは部下に委ね、解決の喜び、自信を与えること
会社の存亡に関わるような問題は別にして、問題の種類によっては部下に任せることが重要だと肝に銘じておくべきだろう。
部下の問題解決能力は、こうした場面に直面することによって磨かれていく。
新 将命