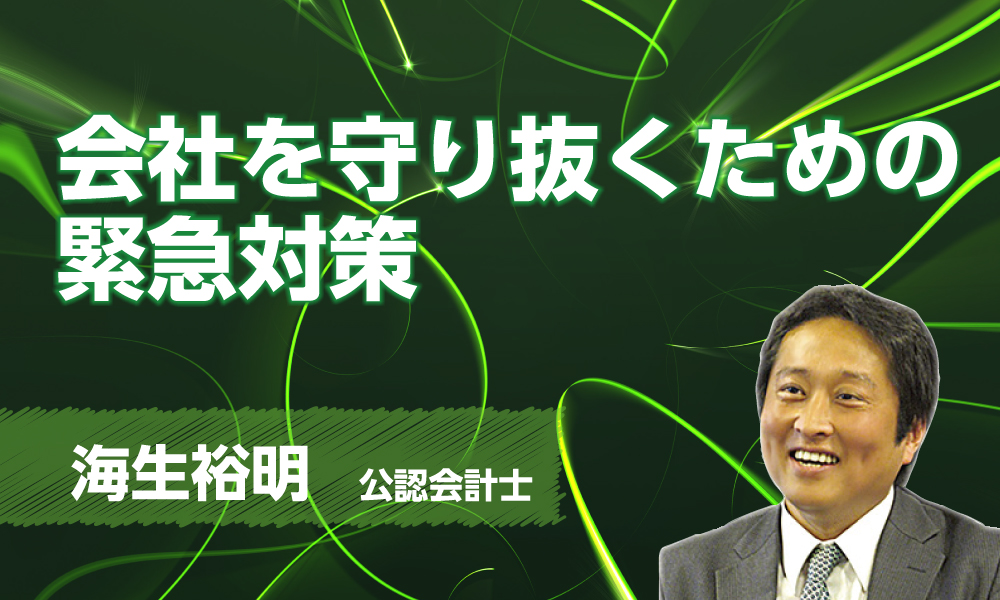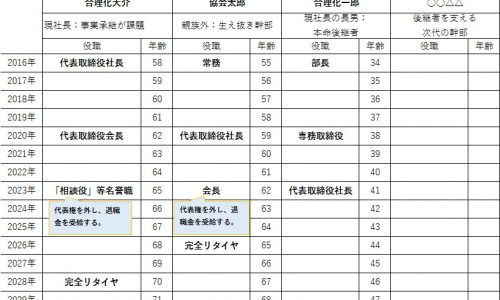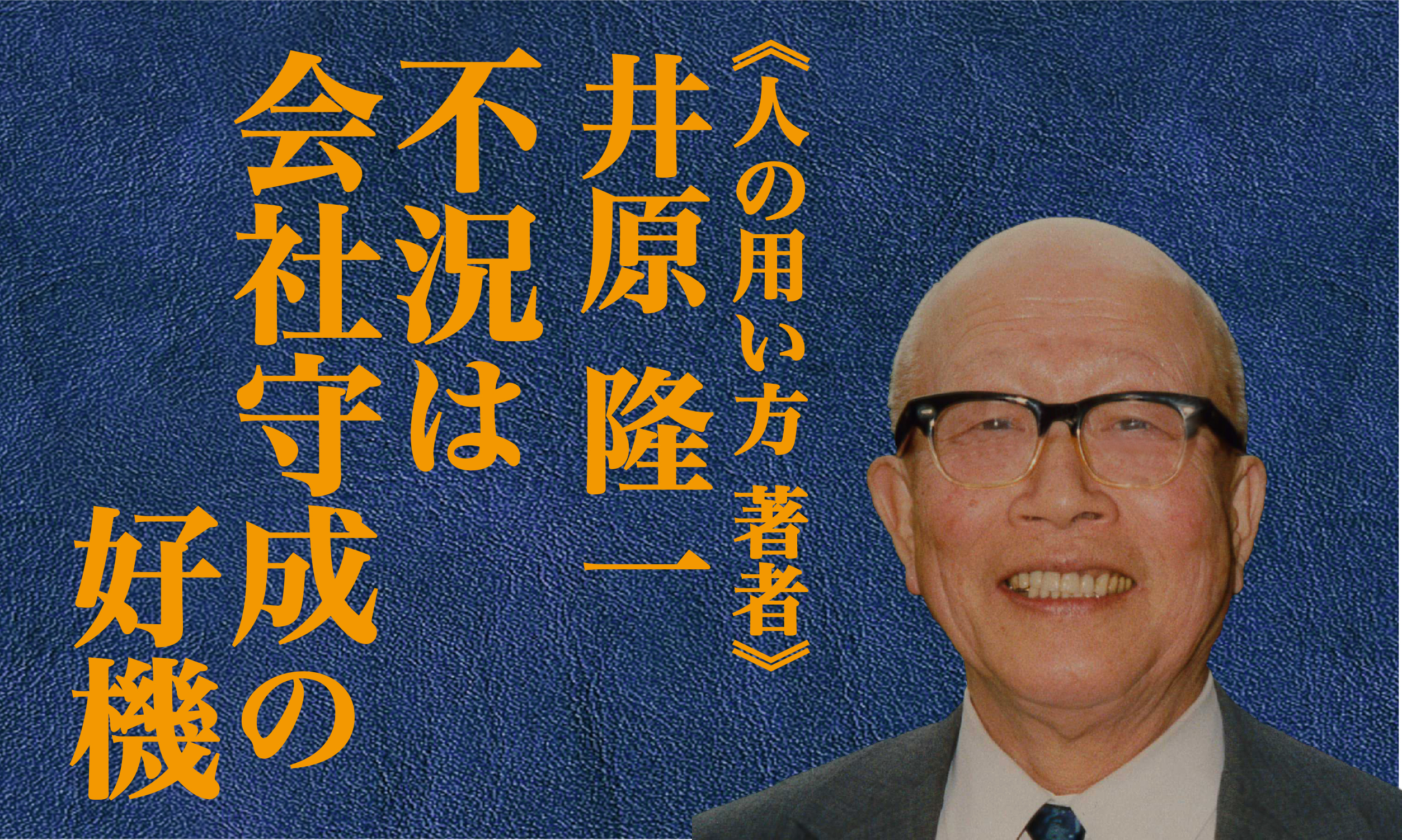
※本コラムは2000年代に井原隆一氏が書き下ろした「不況は会社守成の好機」全41話のコラムを再連載するものです。
“早に今日を知れば何ぞ初めの如くならん”ということわざがある。
早くから現在のように結果を知れば、初めに、あのようにすべきではなかった。という意味だが、私などは結果を知りながら、90歳半ばまで来て悔いている。
唐の政治家張九齢は、“宿昔青雲の志”と詠んでいるが私だってその昔は青雲の志を抱いて“少年老いやすく学成り難し、一寸の光陰軽んずべからず”と朱子の詩をくり返して吟じていたものだったが、
いまでは、夕暮れに捨石に腰を落とし残光を惜しみながら自然に口から出てくるものは同じ朱子の詩“謂うなかれ今日学ばずして、明日ありと、今年学ばずにして来年ありと、日月逝きぬ、歳我を延ばさず、嗚呼老いたりこれ誰のあやまちぞや”自分の学ばず老いに悲しみだけは他のせいにすることはできない、すべては自分の過ちである。
孟子は“人恒(つねに過ちて”、然る後に能く改む。心に困(くる)しみ、慮(おもんばか)りによこたわりて、しかる後におこる。”(人間の多くは過失を犯してはじめてこれを悔い改める。心に苦しみ、思い余ってはじめて奮起する)
失敗や苦しみを体験して悔い改め、奮起するならまだ良いが、何度も改めては悔い、苦しんでは奮起している人もある。私はこれをボーフラ経営といっているが好況時には浮いて不況時には沈んでしまうからで、なんとも頼りない経営といえるだろう。
管子(斉の管仲)に
“いやしくも利を得て後に害有る。愉しくも楽を得て後に憂い有るは、聖人為さざるなり”
(一攫千金を得て後に大損をしたり、怠けて後に心配するようなことを聖人はしない)という意味だが、経営者の悔いの多くは利を先にして義を後にするところから出発しているようである。
※一部旧字を現代漢字に変更させていただいております。






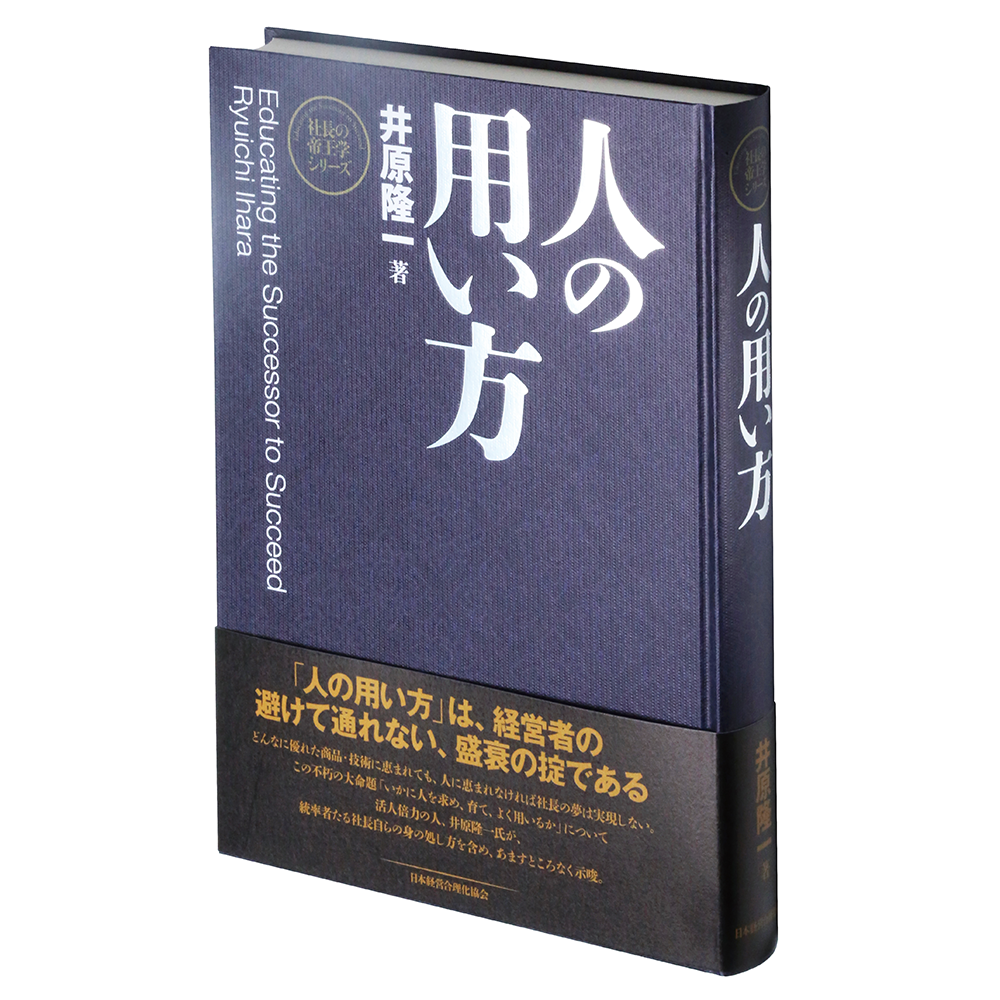
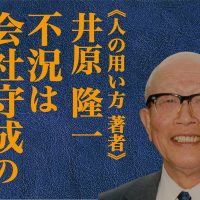
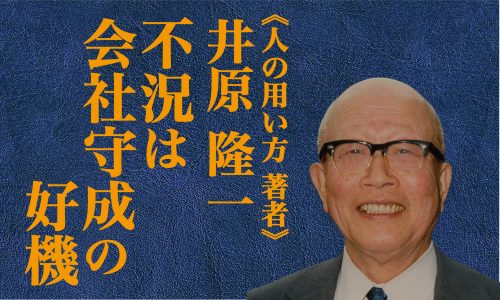

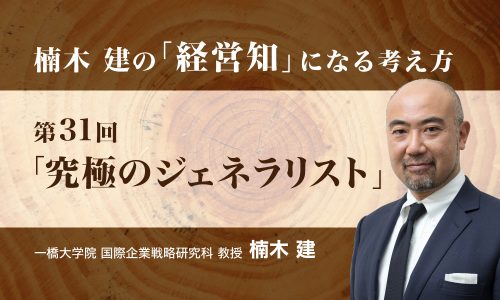
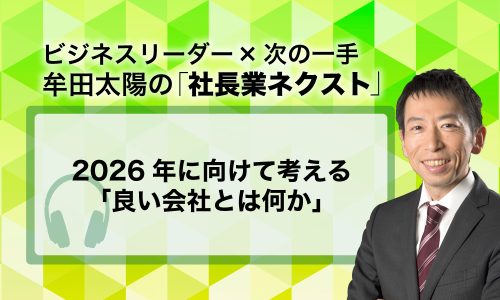


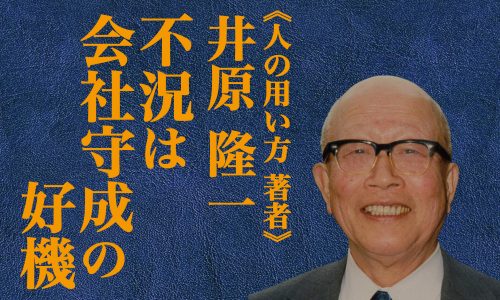



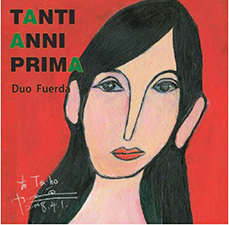

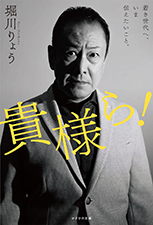
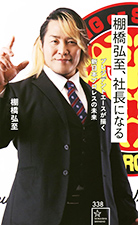



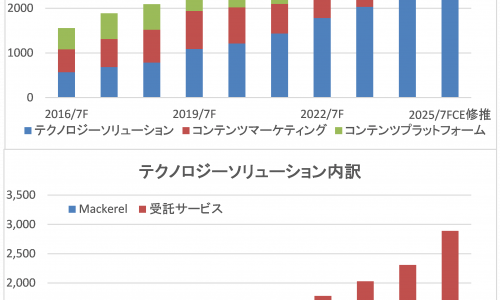



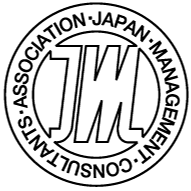

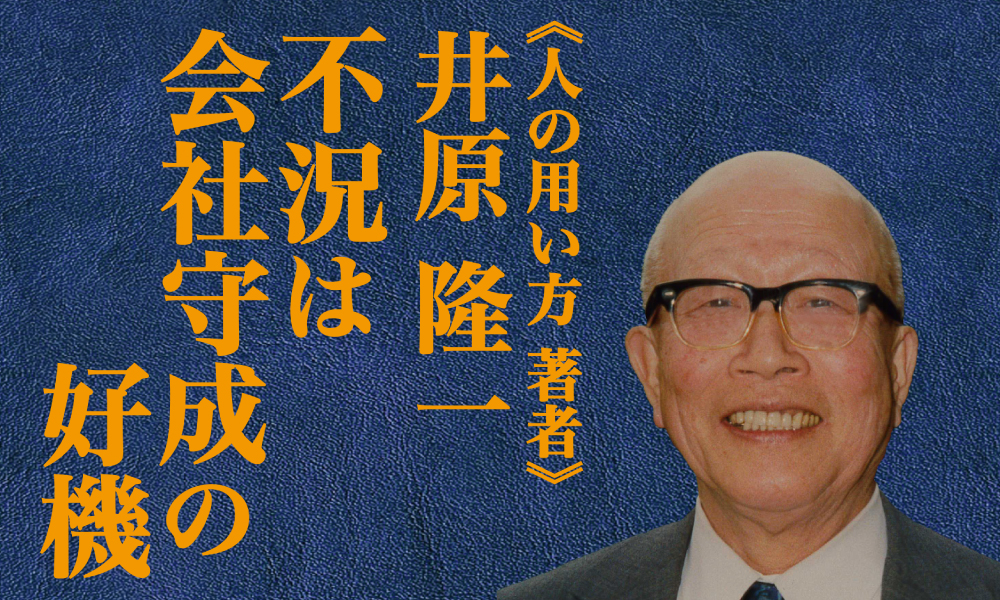
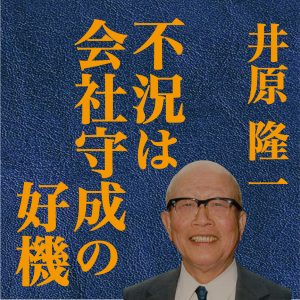


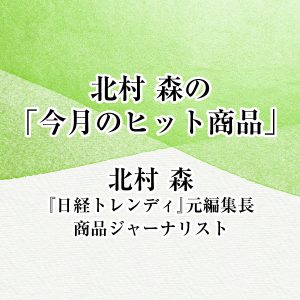




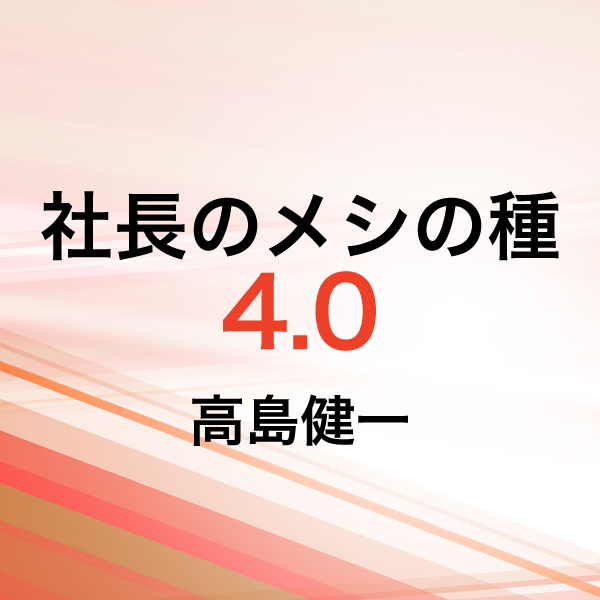

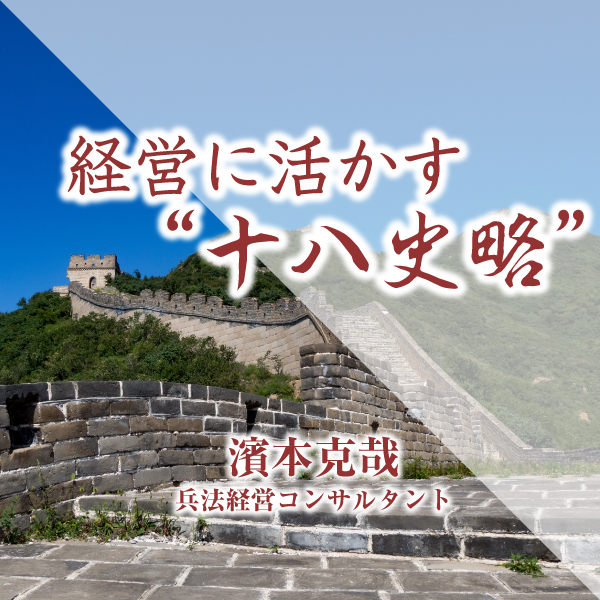

















-1-500x300.jpg)